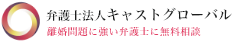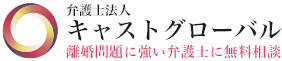離婚手続きの流れと準備を弁護士解説|後悔しないための完全ガイド
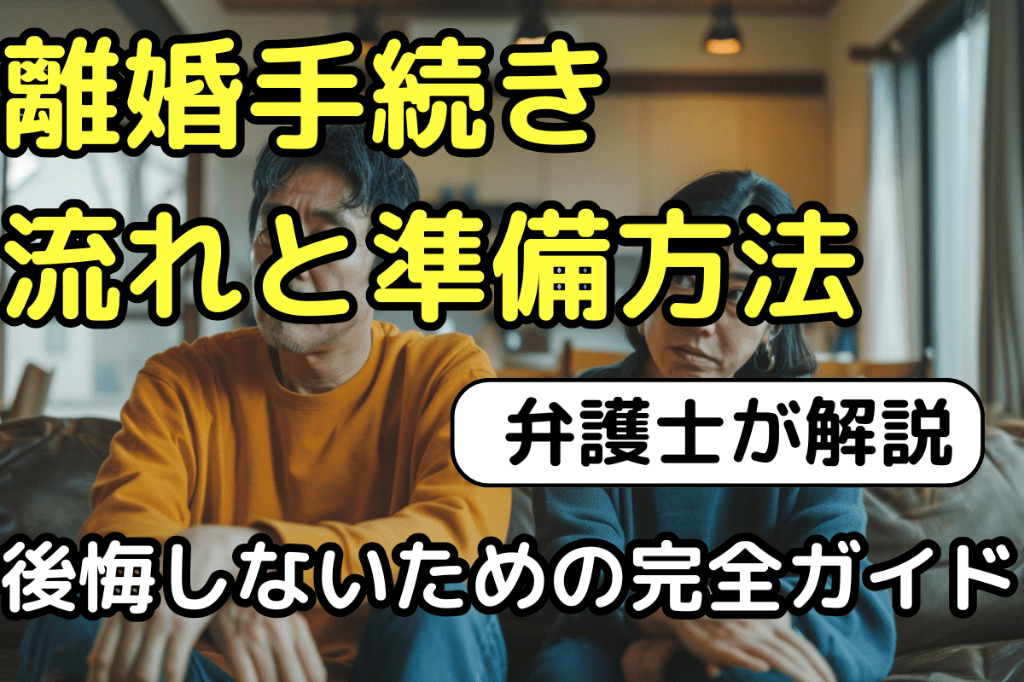

監修者 弁護士法人キャストグローバル
離婚部弁護士
目次
目次を表示はじめに
離婚を考え始めたとき、多くの方が感じるのは「何から手をつけていいかわからない」という不安です。
感情の整理がつかないまま話し合いを進めてしまうと、後で後悔することにもなりかねません。
また、離婚の手続きには「協議」「調停」「裁判」と複数の方法があり、それぞれに進め方・費用・時間・メリット・デメリットが異なります。
本記事では、離婚を考えた段階から、実際の手続き、さらにはトラブルを防ぐ方法まで、弁護士の視点から丁寧に解説します。
これを読むことで、「今の自分がどこから動けばよいのか」「どうすれば後悔しない選択【この記事でわかること】
- 離婚を決める前に整理すべき気持ちと準備のステップ
- 離婚手続きの3つの方法(協議・調停・裁判)の違いと選び方
- 各手続きの流れ・期間・費用・メリット・デメリットの比較
- 離婚協議書の作成方法と公正証書化のポイント
- 調停・裁判での進め方と弁護士が入るメリット
- 各手続きで起こりやすいトラブルとその対処法
- 弁護士に相談すべきタイミングと相談時のチェックポイント
離婚は、人生の中でも特に大きな決断のひとつです。
しかし、多くの人が「感情的に限界を感じたから」「もう無理だと思ったから」といった勢いで動き出してしまい、
その後に「もう少し準備しておけばよかった」と後悔するケースも少なくありません。
離婚を後悔しないために、次の章で詳しく解説します。
1.離婚を決める前にやるべき準備と心構え
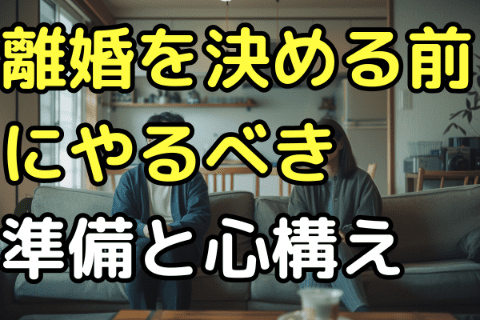
離婚をするかしないかという重大な決心をする前に、しっかりと準備・心構えをしましょう。
1)離婚を決断するためのチェックポイント
まず、「離婚したい理由」を考えて、言語化できるようにしてください。
そして、次に、「離婚後にどのような状態になっていたい」のかを考えてみてください。
その上で、現在とのギャップを確認し、そのギャップを埋められるように、夫婦関係が改善できないのかを検討しましょう。
女性側は、子どもが生まれたばかりなどのタイミングで気分の高低があるといわれていますので、気分できめてしまわないようにしてください。
- 離婚したい理由は何か
- 離婚後にどのような状態になっていたいのか
- 現在とのギャップ
- 夫婦関係が改善できないのか
2)希望条件を整理し優先順位をつける
離婚をするかの決断ができたら、現在と希望のギャップから離婚の希望する条件を整理します。
例えば次のような希望条件があります。
- 子どもの親権を得たい
- 子どもと月◎回会いたい
- 養育費は◎円ほしい(できるだけ高く確保したい)
- 留学、私学に進学などの都度学費を補填してほしい
- 財産分与で自宅が欲しい
- 財産分与で◎円欲しい
- 今の家に住み続けたい
- 不貞などの慰謝料を◎円欲しい
これらの希望条件がでそろったら、これらの条件の優先順位をつけましょう。
3)財産、不貞などの証拠を確保する
離婚において大きな問題となる一つが財産分与です。
相手の財産を把握できている場合は良いのですが、出来ていない場合は財産の証拠を確保します。
また、相手に不貞が疑われている場合において、不貞の証拠を確保しましょう。
相手に離婚を伝えてしまうと相手も離婚の準備を始めますから、財産や不貞に警戒するようになります。
相手が警戒してしまうと、証拠を探すことが難しくなります。
ですから、相手が警戒がなく脇が甘い間に証拠をそろえておきましょう。
財産については次のような証拠を探します。
残高までがわかるものが望ましいですが、どこに財産があるのかがわかる程度のものでも大丈夫です。
- 通帳
- 振込票
- 金融機関から送られてくる通知いずれの証拠も
- 相手が口にした金融機関名
- 固定資産税の納税通知書
- 車検証
不貞については次のような証拠を残します。
- LINE、メールなどのテキストデータまたは写真
- 録音、録画
- ホテルなどの明細書
- スマホ、車の位置情報
- 日記、メモ
- 医療記録、診断書
これらの証拠を確保しておいて、いざとなったら使えるようにしておきましょう。
2.離婚手続きとそれぞれのメリット、デメリット
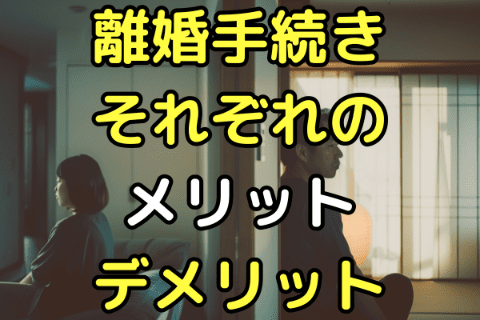
離婚の手続きの流れやその詳細を解説します。
1)離婚手続きには、協議、調停、裁判がある
離婚の流れは、話し合いをする(協議)、裁判所を通じた話し合い(調停)、離婚訴訟があります。
| 手続き | 主な進め方 | メリット | デメリット | 費用目安 |
| 協議 | 当事者で話し合う | 最も早く・安く離婚できる。裁判所を通さず簡単。柔軟な合意内容を決められる | 合意できないと進まない。口約束だとトラブル化しやすい。財産分与・養育費が不明確になりやすい | 書類費用数百円程度 |
| 調停 | 裁判所で調停委員を介して話し合う | 第三者(調停委員)が仲介。話し合いが整理されやすい。調停調書に法的効力あり | 期日が数回必要で時間がかかる。精神的負担が増す | 申立費用1,200円+郵券代数千円程度 |
| 裁判 | 訴訟で裁判所に判断してもらう | 最終的な法的解決が可能。裁判所に判断を求められる。 | 時間・費用・精神的負担が大きい。特に主張立証する書面の作成が大きい。判決まで2年以上かかることも | 弁護士費120万円以上 |
①協議離婚
協議離婚の主な進め方は、 夫婦間の話し合いで合意できれば離婚届を提出して離婚成立です。
メリットは、当事者間の合意ができさえすればよいため、最も早く安く離婚できます。また、当事者間で柔軟な合意内容を決められます。
デメリットは、話し合うことができないと全く進まない。口約束だとトラブル化しやすい。財産分与・養育費が不明確になりやすいなどです。
費用目安は、ほとんどかかりませんが、弁護士に依頼する場合は80万円〜100万円となります。
②調停
調停の主な進め方は、家庭裁判所で調停委員を介して話し合います。
メリットは、 第三者(調停委員)が仲介してくれるため、話し合いが整理され、当事者間で直接話し合う必要がないことです。
デメリットは、月1回程度しか期日がなく、数回期日が必要であることが多いため、時間がかかります。
費用目安は、調停の申立費用1,200円と切手代数千円程度ですが、弁護士に依頼すると80万円〜100万円となります。
③裁判(訴訟)
裁判離婚の主な進め方は、家庭裁判所に訴訟を起こし、裁判所に判断を求めます。
メリットは、最終的な法的解決が可能であること、裁判での話し合いで合意しやすいことです。
デメリットは、時間・費用・精神的負担が大きく、特に書面作成の負担と時間の負担が大きいです。
判決まで2年以上かかることもあります。
費用目安は、 申立費用数千円と切手代数千円程度ですが、弁護士に依頼すると費用120万円以上かかります。
2)離婚手続きの流れ・進め方
離婚手続きの順番は、協議→調停→訴訟の順番が一般的です。
ですが、協議をしないで、調停に進めるということもあります。
また、過去に協議や調停をしており、別居を長期間していているときなど、いきなり訴訟をするということも稀ですがあります。
一般的な流れでいいますと、次の通りです。
- 離婚の決意を固める
- 離婚条件を整理する
- 離婚条件の優先順位を決める
- 財産、不貞等の証拠・資料収集する
- 話し合い(協議)→合意できれば離婚
- 合意できなければ調停申立て
- 調停合意できず不調→訴訟を提起する
- 離婚後の手続きをする
3.協議離婚の手続きとは何か
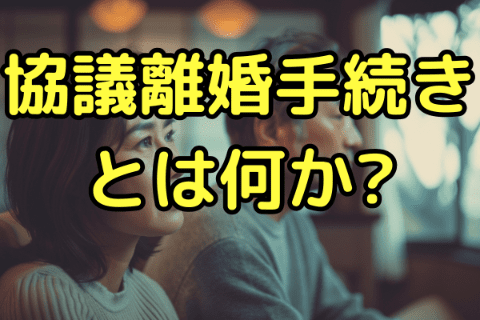
協議離婚の手続きについて解説します。
1)協議離婚の流れと必要書類
協議離婚を含めた全体の流れは、次の通りです。
- 離婚の決意を固める
- 離婚条件を整理する
- 離婚条件の優先順位を決める
- 財産、不貞等の証拠・資料収集する
- 相手に離婚したい旨を伝える
- 相手の離婚についての意思を確認する
- 離婚条件について話し合う
- 合意したら書面化する
協議離婚は、当事者間で協議をして、離婚及びその条件の合意を目指します。
協議での確認事項の第一は、相手が離婚することじたいに合意できるかです。
条件しだいというところはあるかもしれませんが、相手が離婚しても良いとならないと条件の話し合いが難しくなります。
離婚じたいの合意を得られれば、離婚の条件を話し合いましょう。
先だって検討した優先順位を考えながら、譲歩できるところは譲歩して、離婚条件を詰めていきます。
離婚条件がまとまった場合は、離婚協議書として書面化することをお勧めします。
離婚以外に何らの条件もない場合でない限り、後々の紛争を防止するため、離婚協議書の作成は必要不可欠です。
2)離婚協議書のひな形
協議で離婚及びその条件がまとまれば、離婚協議書として書面化します。
一例として、離婚協議書を以下に示します。
離婚協議書(例)
〇〇(以下甲という)と△△(以下乙という)は、甲乙間の婚姻の解消に関する件(以下「本件」という。)について、以下のとおり合意する。
第1条(離婚の合意)
甲及び乙は、本日、協議離婚する。なお、役所への届け出は、乙が行う。
第2条(親権)
甲乙間の長男□□(□年□月□日生)、長女××(×年×月×日生)の親権者・監護者を乙と定めて、乙において監護養育することとする。
第3条(養育費)
1 甲は乙に対し、前記子らの養育費として、〇年〇月から満18歳に達する月まで、1人につき1ケ月〇万円の支払い義務のあることを認め、これを毎月末日限り乙が指定する口座に振込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
2 前記子らが大学またはこれに準ずる高等教育機関(以下「大学等」という。)に進学した場合、前項の養育費の支払いは、子らが大学等を卒業する月までとする。
3 当事者双方は、前記子の病気、進学等の特別の費用の負担については、別途協議する。
第4条(面会交流)
1 乙は、甲が前記子らと月1回程度、面会交流することを認める。
2 面会交流の具体的な日時、場所及び方法については、前記子らの福祉に配慮して、甲及び乙が協議して定める。
3 協議が整わない場合、原則として面会交流は以下の通りとする。
日時: 毎月第1、第3週の土曜日及び日曜日、土曜日午前10時から日曜日午後5時まで。
方法: 甲が、乙宅または保育園、学校へ子らを迎えに行き、面会交流終了後、同所また
は乙の指定する場所へ子らを送る。
第5条(財産分与)
甲は、乙に対して、離婚に伴う財産分与として、◎円の支払い義務があることを認め、◎日までに振り込む方法によって支払う。
第6条(年金分割)
甲は乙に対し、甲乙の婚姻期間中における双方の年金分割の割合を0.5とし、その年金分割に必要な手続きに協力する。
第7条(清算条項)
甲及び乙は、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、相互に何らの財産上の請求をしない。
第8条(公正証書)
甲及び乙は、本件離婚協議書と同趣旨の強制執行認諾文言付公正証書を作成することに合意した。
以上の合意成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙が署名捺印の上、各自1通を保有する。
〇年〇月〇日
(甲)住所
氏名 印
(乙)住所
氏名 印
書面化するに際して、公正証書にするかどうかということを検討してください。
強制執行認諾文を添えた公正証書にするメリットは、強制執行を容易にすることです。
訴えを提起して、自己の権利が認められる判決を獲得してからでないと、強制執行することができません。
ですが、強制執行認諾文付公正証書とすることで、訴訟を起こして判決を取る必要がなくなります。
養育費の支払いなど金銭の支払いが将来に残り、その支払いに不安が残る場合は、強制執行認諾文付公正証書にすることをご検討ください。
4.調停離婚の手続きとは何か
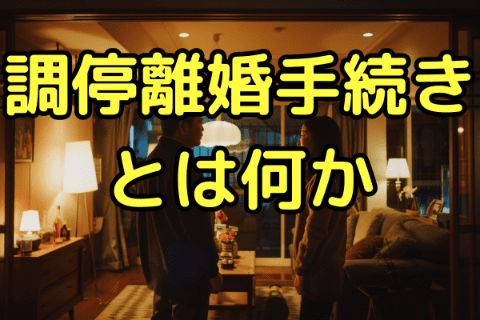
調停離婚の手続きとは、裁判所を介した話し合いにより、双方が離婚及びその条件を話し合う手続きです。
裁判所でやるものの、あくまでも話し合いですから、比較的ハードルが低く、多くの方が選択される手続きです。
協議による手続きで合意に至らなかった場合、協議そのものができそうにない、協議にならない場合などに調停離婚の手続きを選択します。
1)調停離婚の手続きと流れ
調停離婚の手続きを含めた全体の流れは、以下のような流れです。
- 離婚の決意を固める
- 離婚条件を整理する
- 離婚条件の優先順位を決める
- 財産、不貞等の証拠・資料収集する
- 相手に離婚したい旨を伝える
- 相手の離婚についての意思を確認する
- 離婚条件について話し合う
- 合意が出来そうにない、感情的になって話し合いにならない
- 裁判所に調停を申し立てる
- 一月半に一回程度、裁判所にて話し合いをする
- 合意したら裁判所において書面化してくれる
離婚準備ができれば、相手に離婚の意思を伝えます。
相手が離婚なんて絶対に嫌だとか、感情的になって話し合いが出来そうもないという場合に、調停を申し立てます。
裁判所においての話し合いは、期日と呼ばれ一月半に一回程度となります。
2)調停離婚の特徴と費用
調停離婚の手続きの目的は、話し合いによる合意を目指すことです。
そのため、調停委員が当事者の間に入って、話し合いを進めてくれます。
第三者が間に入ってくれること、裁判所であることから、互いに感情的になりにくいです。
また、調停委員が、相手に対して譲歩を求めたり、こちらに提案してくれる場合もあり、まとまりやすいといえます。
そして、合意できれば、離婚及びその条件を調停調書として書面化してくれます。
調停調書をもって強制執行ができるために、その内容に強制力があります。
とてもメリットが大きい反面、デメリットとしては、一月半に一回の期日となるため、進行がかなり遅くなることです。
費用は、数千円の切手代と1,200円の印紙代を裁判所に納める程度で足ります。
ですが、より優位に進めるために弁護士に依頼すると、合計で100万円程度は必要となります。
5裁判離婚の手続きとは何か

裁判離婚の手続きとは、裁判所に離婚を求め、裁判所に判断してもらう手続きです。
これまでと異なり、当事者間での話し合いではなくなります。
調停による手続きで合意に至らなかった場合などに裁判離婚の手続きを選択します。
1)調停離婚の手続きと流れ
調停離婚の手続きを含めた全体の流れは、以下のような流れです。
- 離婚の決意を固める
- 離婚条件を整理する
- 離婚条件の優先順位を決める
- 財産、不貞等の証拠・資料収集する
- 相手に離婚したい旨を伝える
- 相手の離婚についての意思を確認する
- 離婚条件について話し合う
- 合意が出来そうにない、感情的になって話し合いにならない
- 裁判所に調停を申し立てる
- 一月半に一回程度、裁判所にて話し合いをする
- 調停で合意できず不調に終わる
- 裁判所に離婚を求めて訴えを提起する(裁判離婚)
- 期日において互いに主張立証する
- 裁判官が判断をする
裁判離婚の手続きの目的は、裁判所に判断を求めて、その結果に強制力を求めることです。
期日は、調停と同様に、一月半に一回程度です。
2)裁判離婚の特徴と費用
裁判離婚は、裁判所に判断をゆだねることが出来、裁判所に判断されてしまうという特徴があります。
ですが、全く話し合いができないということはなく、期日に裁判所から和解をしないかとすすめられることが何度かあるでしょう。
ですから、裁判離婚に進んでも、判決ではなく和解で終わるということも多く見られます。
調停と同様に期日が一月半に一度のため、時間がかかるという特徴があります。
相手が約束を守らず期日の準備を怠ったりすると、期日が空転することがあり、さらに時間がかかります。
訴訟を申し立てる費用は、13,000円程度の印紙代と数千円の切手代になります。
弁護士に依頼する場合は、合計で120万円以上必要となります。
5.各手続きで起こりやすいトラブルとその対処法

各手続きにおいて、起こり易いトラブルとその予防法を解説します。
1)協議離婚で起こりやすいトラブルとその予防法
協議離婚で起きやすいトラブルとその対処法は次の通りです。
- 離婚と親権者以外を決めずに離婚した
- 離婚に関するすべての条件が整うまで離婚しない。
離婚以外の条件で争いが残ります。
離婚をしたい側にとってはこれで目的が果たせるので、急ぐ必要がなくなります。
戦略的にする場合でない限り、すべての条件をまとめてから離婚しましょう。
- 離婚に関するすべての条件が整うまで離婚しない。
- 合意結果を書面に残していない
- 離婚協議書を作成して下さい。
書面に残さないと、いったいいわないの話が出てきますし、書面にしないことで詳細が詰め切れていないことが多く、あとあと紛争になります。
- 離婚協議書を作成して下さい。
- 書面に残したが文面が不適切
- 離婚条件がまとまったら、書面化だけは弁護士に依頼する。
書面をしっかり残していても、素人が作った書面だと相手に履行を求めることができない定めなど、強制力のないものがあります。
- 離婚条件がまとまったら、書面化だけは弁護士に依頼する。
2)調停離婚で起こりやすいトラブルとその予防法
調停離婚で起きやすいトラブルとその予防法は次の通りです。
- 相手が出廷してこない
- 調停に出てこないと裁判せざるを得ないと事前に伝えておきましょう。
- 面会交流条件が間接強制できない定め
- 弁護士に文言を相談する。
裁判所で定めた文言だから何らの不備もないということではありません。
不備もとらえる人によっては不備ではないからです。
- 弁護士に文言を相談する。
- 調停委員が片方の肩を持ちすぎる
- 調停員がどういう思考の持ち主か観察して、こちらの肩を持ってもらうようにする。
- 調停委員が話を理解しようとしない
- 調停員の考え方を理解して、それに沿って主張する。
- 調停員か自分の考えを押し付ける
- 論点、見る方向を変える。
3)裁判離婚で起こりやすいトラブルとその予防法
裁判離婚で起きやすいトラブルとその予防法は次の通りです。
- 主張立証が適切にできない
- 要件に対する事実と評価をしっかり区別して記載する。
- 裁判官の求めているものをだしていない
- 裁判官の話をよく聞き、裁判官が求めていることをまず第一に答える。
- 面会交流条件が間接強制できない定め
- 弁護士に文言をレビューをしてもらう。
6.弁護士に相談すべきタイミングと活用法

弁護士に相談すべきタイミングとその活用方法があります。
- 離婚を決意したタイミングで、相手にその意思を伝える前
- 専門家である弁護士に相談することで、離婚に向けた準備をしっかり整えることができます。
- 協議を始めたが、相手が話し合いに応じてくれない、または感情的になるなどで話し合いにならない場合
- 第三者の専門家である弁護士に依頼すると、弁護士があなたに代わって相手と交渉します。
相手は当事者でない第三者であることから感情的にならず話し合えます。 - 専門家である弁護士が入ることで、交渉があなたに有利にすすむことが紀伊出来ます。
- 第三者の専門家である弁護士に依頼すると、弁護士があなたに代わって相手と交渉します。
- 協議において条件がまとまらない場合
- 専門家である弁護士に依頼することで、条件がまとまる可能性が高くなります。
- 条件がまとまらなければ、調停に進めるのが得策であるところ、調停の申し立てなどを弁護士に任せることができます。
- 調停において自分に有利に進んでいないと感じたとき
- 調停委員は中立第三者であるべきなのですが、自分の考えをおしつける人、譲歩しやすい側に譲歩させようとする人など、とうてい中立とはいえない人が結構います。
ですが、弁護士が入ることで、偏った調停委員の意見を押しのけて話を進めることができるようになります。
- 調停委員は中立第三者であるべきなのですが、自分の考えをおしつける人、譲歩しやすい側に譲歩させようとする人など、とうてい中立とはいえない人が結構います。
- 調停が不調に終わったとき
- 調停が不調に終わると、離婚については訴訟をするか、いったん諦めるかということになります。
弁護士に依頼することで、証拠を精査して訴訟の準備を適切に進めることができます。
- 調停が不調に終わると、離婚については訴訟をするか、いったん諦めるかということになります。
弊所では初回相談無料ですから、上記のタイミングでご相談いただければお力になれると思います。
まとめ
離婚は、感情的にも経済的にも大きな決断です。
しかし、正しい手順と準備を踏めば、トラブルを最小限に抑え、安心して新しい生活をスタートさせることができます。
まず、重要なのは、「勢いで離婚に踏み切らないこと」です。
離婚を決める前に、自分の気持ちを整理し、離婚後にどのような生活を送りたいのかを明確にしておくことが大切です。
そのうえで、希望条件(親権・養育費・財産分与・慰謝料など)を整理し、優先順位をつけておくと、協議や調停でぶれない軸ができます。
また、財産や不貞などの証拠を確保することは、今後の交渉・裁判を有利に進める上で欠かせません。
通帳や固定資産税通知書、LINE・メールなどのデータは、相手が警戒する前に集めておくのがポイントです。
離婚の手続きには「協議」「調停」「裁判」の3つの方法があります。
話し合いで合意できれば協議離婚、感情的な対立があれば家庭裁判所での調停離婚、それでもまとまらない場合は裁判離婚へ進みます。
それぞれにメリット・デメリットや費用・期間の違いがあるため、自分の状況に合わせて選択することが重要です。
そして、どの段階でも「弁護士への相談」が非常に有効です。
離婚を決意した段階や、協議が進まない・調停が不利に感じるときに弁護士へ相談することで、法的な根拠を踏まえた最適な戦略を立てることができます。
また、弁護士が代理人となることで、精神的負担を軽減し、冷静な判断がしやすくなります。
離婚は「終わり」ではなく「再スタート」です。
焦らず、準備・整理・専門家の活用を意識することで、あなたにとって最善の形で次の人生を歩み出すことができます。
関連ページ