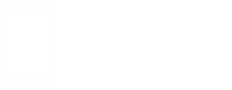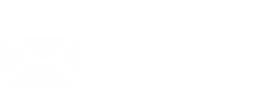- 最終更新:
遺産分割での不動産の3つの評価額・評価方法!基準時についても解説

相続で不動産が含まれていると、
「この家や土地はいくらの価値があるのか?」
「どう分ければ公平なのか?」
といった疑問や不安に直面する方がとても多いです。
不動産は現金のように単純に分けられず、評価の仕方によって金額が大きく変わることがあります。評価が違えば、受け取れる相続分や支払う代償金の額も変わり、トラブルに発展してしまうことも少なくありません。
この記事では、不動産の評価がなぜ重要なのか、その具体的な方法や注意点、さらに相続人同士で揉めないための実践的なポイントをわかりやすく解説します。
【この記事でわかること】
- 遺産分割における「不動産の評価額」とは、現金化した場合の価値の見積りであること
- 評価方法によって金額が変わるため、相続人間でどの方法を採用するかが重要となる
- 不動産評価には、以下の3つの基準があること
- 不動産鑑定評価額(最も実勢価格に近く、公平性が高い)
- 固定資産税評価額(納税用の額で、実勢より低い)
- 相続税評価額(相続税計算用で、こちらも実勢より低い)
- 不動産鑑定評価では以下の4つの手法が用いられること
- 原価法(再調達価格から減価修正)
- 取引事例比較法(類似不動産の取引事例との比較)
- 収益還元法(将来の収益を現在価値に割り戻す)
- 開発法(開発後の売却価額から費用を控除)
- 遺産分割における評価基準時点は、実務上「分割時点」が基準となる。ただし寄与分や特別受益の計算では「相続開始時(死亡時)」が基準
- 遺産分割協議の進め方と注意点
- 遺言書の有無の確認、相続人・遺産の確定、相続人全員での協議が必要
- 情報を共有しないと不信感が生まれ、骨肉の争いに発展するリスクがある
- 評価方法による違いとトラブル例
- 固定資産税評価額や相続税評価額は「低め」であり、公平性に欠けて揉めやすい
- 不動産鑑定評価額は公平だが、評価者や手法で差が出るため合意が必要
- 代償分割では「取得者は安く評価したい」「受取者は高く評価したい」と利害が対立する
- 専門家の役割は、税理士=相続税申告、司法書士=登記、不動産鑑定士=評価、弁護士=交渉・調停対応
- 相続人同士で合意できない場合や調停・裁判に進む場合は弁護士に相談すべき
不動産の遺産分割の方法について詳しく知りたい方は、「不動産を遺産分割する4つの方法とは?円満な分割のコツと流れを解説」をご覧ください。
目次
1.遺産分割での不動産の評価とは?評価が重要な理由は?
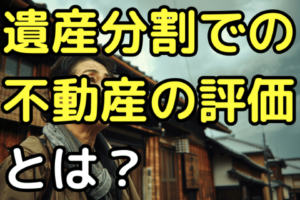
まず前提として、遺産分割における不動産の「評価額」とは、不動産を現金化したらいくらになるのかという不動産の価値を見積もった額のことをいいます。
不動産を評価する方法は複数あり(2章で解説)、評価方法によって価格も変わります。
相続人間の話し合いにおいて、どの評価方法を採用して価格をいくらとするかを決めます。
1)評価が重要な場面①:不動産を現金化して相続する場合
不動産を現金化して相続する場合は、当然ながら評価がいくらであるかが重要になってきます。
特に不動産の評価が特に重要なのは、不動産を「代償分割」で分ける場合です。
「代償分割」とは、不動産を相続人した人が、その不動産相当額を他の相続人に支払うことをいいます。
この場合、不動産を相続した人が「支払う金額」、不動産を相続しなかった人が「受け取る金額」はその不動産の評価額です。
ですから、代償分割を考えている相続人の方には、これから解説する評価の仕方が非常に重要になってきます。
2)評価が重要な場面②:相続税の計算・申告をする場面
不動産の相続税の基礎となる額は、「相続・・・により取得した財産の価額」(相続税法11条の2)、市場価格ということになります。
ですが、市場価格を決めるというのは、実際に市場で売却してみないと見積もるのは困難です。
そこで、不動産の相続税における価額は、土地については路線価方式または倍率方式で決まり、建物については固定資産税評価額と同額となります。
この額に特例などを反映して相続税における価額が決まります。
2.不動産相続における3つの評価方法・評価額
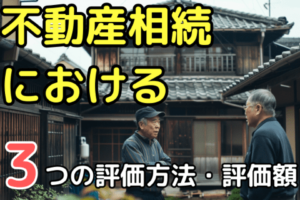
よく耳にする不動産の3つの評価について、解説します。
【3つの評価額】
- 不動産鑑定評価額
- 固定資産税評価額
- 相続税評価額(路線価)
先に述べると、実際の評価額として採用するべきなのは1つ目の「不動産鑑定評価額」です。
後の2つの評価額は、あくまで参考としてチェックするのがおすすめです。
1)不動産鑑定評価額
不動産鑑定評価額とは、その不動産が実際に取引されるであろう価格をいいます。
不動産鑑定士、不動産売買仲介会社などで算出してもらうことが出来ます。
先にも述べましたが、不動産の換金(代償分割や換価分割)を前提にするなら、この評価額を採用するのがベストです。
不動産が実際に取引されるであろう価格を「実勢価格」といい、これが最も「今の不動産の価値」として正確だからです。
不動産が実際に取引される価格を実際に取引せずに正確に算出することは不可能です。
なぜなら、欲しい人はその欲しい人が出せるだけのお金を出してでも欲しいのであり、その金額を予想するというのは不可能だからです。
ですが、不可能といってやらないということはできないので、出来る限りその価格を予想するための方法が4つあり、原価法、取引事例比較法、収益還元法、開発法となります。
➀原価法
不動産の再調達原価(現時点で同じものを新たに建設・造成する場合の費用)を算出し、経年による減価修正を行って価格を求める方法です。
主に建物や一戸建て、造成地などに用いられます。
②取引事例比較法
類似不動産の実際の取引事例を収集し、地域要因、個別要因や事情補正・時点修正を考慮して比較し、対象不動産の価格を推定する方法です。
マイホームや店舗、事務所など、同一需給圏内で類似取引がある場合に有効です。
③収益還元法
不動産が将来生み出すと期待される純収益(家賃収入等)を一定の利回りで割り引き、現在価値を算出する方法です。
主に投資用不動産や賃貸物件、収益物件の評価に用いられます。直接還元法やDCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)などの手法があります。
④開発法
大規模な土地などで、開発後に販売される宅地等の総額から造成費や建設費、その他の費用を控除して価格を求める方法です。主にマンションや分譲住宅、開発用地の評価に用いられます。
2)固定資産税評価額
固定資産税評価額とは、固定資産税を算出する際の不動産の価格です。
固定資産税とは、1月1日現在、不動産、船舶などの資産を所有している人に対してかかる市町村税です。
4月から5月に、その不動産がある市町村から、1月1日現在の所有者に対して、納税証明書が届きます。
納税証明書には、課税明細書がついていて、課税明細書に各不動産の価格が記載されています。
この価格が固定資産税評価額です。
遺産分割の際に、固定資産税評価額を参考にするにはいいですが、遺産を分割する際の価格にするには適していません。
なぜなら、固定資産税評価額は、実際に取引されるであろう時価よりも低くなるからです。
3)相続税評価額
相続税評価額とは、相続税を算出する際の不動産の価格です。
相続税とは、亡くなった親などから財産を受け継いだ際に、その受け継いだ財産にかかる国税です。
そして、相続税評価額は、土地であれば路線価方式または倍率方式により算出され、建物であれば固定資産税評価額と同額になります。
固定資産税評価額と同様に、実際に取引される時価よりも低くなるため、遺産分割の際に、相続税評価額を参考にするのはいいのですが、遺産を分割する際の価格にするには適していません。
3.不動産の遺産分割における「基準時」とは?
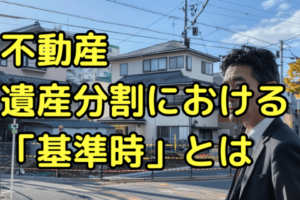
不動産の遺産分割における「基準時」とは、不動産の価値(=評価額)をどの時点の価格で見るかという基準をいいます。
不動産の価格は、瞬間瞬間で変わっていくものであり、どの時点をとるかで価格が変わります。
そして結論、不動産の遺産分割における基準時は、実務上、遺産分割する時点です。
ただし、寄与分、特別受益においては、相続が開始した時点(被相続人が死亡した日)が基準となります。
基礎を説明し終えましたので、具体的な遺産分割における方法をお伝えします。
4.不動産を含む遺産分割の具体的評価と実践テクニック
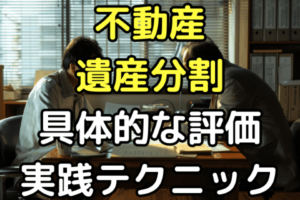
どの評価を用いてどのような方法で遺産分割をすすめるのかを解説します。
1)不動産を含む遺産分割協議の進め方
遺産分割の進め方は次の通りです。
- 遺言書の有無を確認する
- 自筆証書遺言の場合は、検認手続きをする
- 相続人が誰かを確定させる
- 遺産を確定させる
- 遺産分割協議をする
- 遺産分割調停・審判
- 遺産分割を実行する
遺産分割協議を進めるにあたって、まず初めにすることは遺言書があるかどうか確認です。
自筆で書いた遺言書がないか探してみる、公正証書役場において公正証書遺言がないかなど確認してください。
次に、どのような財産を誰と分けるのかを確定させます。
遺産分割は相続人全員の合意が必要ですから、相続人が誰であるかを確認します。
実は知らないところで子どもを持っていたということも稀にありますから、戸籍を遡って確認してください。
ここまで整ったら、相続人全員と遺産分割協議をはじめましょう。
遺産分割協議を始めるにあたっての注意点があります。
被相続人が死亡した時点から出来る限り相続人全員と情報を共有することです。
被相続人が死亡時点から遺産分割協議を始めるまでの間の情報が共有できていないことを発端として大きなトラブルに発展します
相続人の誰かが、他の相続人が不正をしている不公平な取り扱いをしていると思うと、あらゆることに疑念を抱かれてしまい、それが大きくなって骨肉の争いになります。
2)遺産分割協議における不動産の評価方法
遺産分割協議において、不動産の評価額を固定資産税評価額、相続税評価額とするのは適当ではありません。
なぜなら、これらは税金の算出のための基礎額で、実際の価格より低く設定されているからです。
ですが、一つの目安としてこれらの評価額を使うことは出来ます。
例えば、固定資産税評価額を0.7で割り戻すと取引額の目安とされています。
不動産鑑定評価にお金をかけるほどの不動産ではない、田舎で近隣に同種の不動産がないなどの場合に簡易計算できるこの方法を使うことがあります。
遺産分割調停においては、地元の不動産会社の評価額などを利用することが多く見られます。
この評価額で相続人の合意が得られない場合は、裁判所が選任した不動産鑑定士による鑑定評価が用いられます。
裁判所が選任した不動産鑑定士は、上で解説した4つの方法を用いて評価します。
3)遺産分割の具体例で学ぶ!不動産評価が結果をどう変えるか
不動産の評価はとても難しく、遺産分割協議に限らずですが、もめることが多いです。
なぜなら、不動産は、比較的金額が大きくなるし、同じものが2つとない唯一無二の物であって、その正確な価格は実際に市場で売ってみない限りわからないからです。
- 相続人全員で話し合うこと
- 相続人全員が同じ情報を共有すること
- 何かあれば都度報告すること
具体的事例をもとにお話します。
ケース1:固定資産税評価額で分割した場合
固定資産税評価額じたいが多くの方に知られています。
ですが、固定資産税評価額がどのように算出されていて、実際に取引されるであろう価格とは乖離があるということを認識されていない方が多いです。
ですから、固定資産税評価額で不動産を評価することで合意した後に、固定資産税評価額が実際に取引されるであろう価格より低いことを知ったなどして紛争になることがあります。
また、固定資産税評価額を不動産の評価としないかと提案した相続人が、そんな不公平な提案をするのかと紛争になります。
どうして固定資産税評価額を選びたいのか、固定資産税評価額とは何かを相続人全員で共有していれば、起きなかった問題かもしれません。
ケース2:相続税評価額で分割した場合
このケースもケース1と同様です。
相続税評価額が何か、どういうものかを相続人間で共有することが大切です。
ケース3:不動産鑑定評価で分割した場合
不動産鑑定評価は、実際に取引されるであろう価格です。
ですから、公平な分割といえます。
しかし、不動産鑑定評価は、上記で説明したとおり4つあり、これらの組み合わせでも算出するなど、方法は複数あります。
また、鑑定評価者の考え方が反映されます。
よって、不動産鑑定評価には、誰がどのように評価したかによって、評価額に大きな開きがあります。
したがって、結局のところ、いくらにするかということでもめることになります。
5.不動産の分割方法で揉めるケースとは?
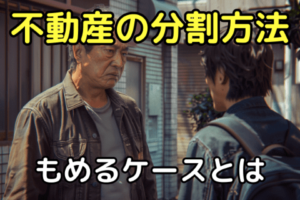
評価方法でもめるケースを解説しましたが、分割方法でもめる代表的なのは、「代償分割」です。
代償分割とは、相続人の誰かが不動産を取得し、不動産価格分を現金で他の相続人に分ける方法です。
この場合、不動産を取得する相続人は、不動産を安く評価したいし、代償金を受け取る相続人としては、不動産を高く評価したいです。
つまり、相続人間において、不動産をいくらと評価するかでもめることになります。
これを回避するためには、事前に情報を共有して、どういう方法で評価するかを合意し、だれも関わったことがない第三者の専門家に依頼し、その評価は誰も不平を言わないと決めることです。
6.トラブルを回避・解決する専門家の活用術
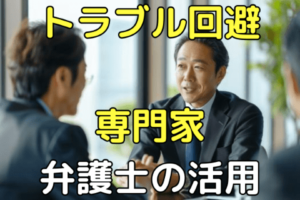
これまで申し上げた様々なトラブルの種をすべて回避するというのはとても難しいことです。
そこで検討してほしいのは、弁護士などの専門家を利用することです。
1)誰にどの相談をするのか?不動産で頼れる専門家の種類と役割
誰にどの相談をするのが適切なのかを解説します。
【税理士】:税務申告の専門家です。
税理士であっても、法人税、所得税と資産税で専門が分かれています。
相続税申告をお願いするとしたら、資産税(相続税)を専門にされている方を探してください。
遺産分割協議がまとまった時、遺産分割協議が被相続人が死亡してから10ケ月以内にまとまりそうもない時に相続税申告を依頼します。
【不動産鑑定士】:不動産評価の専門家です。
裁判においても裁判所から鑑定を依頼されたり、国などが示す評価の基礎となる公示価格を算出しています。
不動産の取引されるであろう価格を評価してほしいときに依頼します。
【司法書士】:登記の専門家です。
登記には、商業登記と不動産登記がありますが、司法書士はいずれであっても専門的に対応しています。
遺産分割協議がまとまった後に、不動産の相続登記を依頼します。
【弁護士】:法律の専門家で唯一あなたに代わって交渉ができます。
弁護士の業務は相当に広いため、遺産分割について専門的に扱っている方を選んでください。
2)専門家への相談タイミング
遺産分割協議がすんなりまとまった時は、不動産がある場合は司法書士さんに登記を依頼し、相続税申告を税理士さんに依頼するのがいいでしょう。
いずれの手続きもご自分でも対応したいという場合は、登記は法務局に相談、税務申告は政務所に相談することでも対応は可能です。
ですが、税務申告については、減税措置を見逃して多額の相続税を払うことになっては大変ですから、この点は慎重にお願いいたします。
遺産分割協議がまとまらない、特定の相続人が遺産を隠匿、浪費している、生前に多額の援助を受けているなどの場合は弁護士に相談されることをおすすめします。
また、遺産分割調停などの裁判手続きに入る場合には依頼をおすすめします。
まとめ
不動産を含む遺産分割は、単純に分けられない財産であるがゆえに、相続人同士で最も揉めやすいテーマです。
その根本には「不動産をいくらと評価するか」という問題があります。
評価方法によって金額が変わり、代償分割で支払う金額や相続税の負担額に直結するためです。
不動産の評価には「不動産鑑定評価額」「固定資産税評価額」「相続税評価額」がありますが、実際の取引価格に最も近く、公平性が高いのは不動産鑑定評価額です。
固定資産税評価額や相続税評価額はあくまで税金算出の基準であり、実勢価格より低めに設定されているため、遺産分割の基準にするには注意が必要です。
相続で大切なのは、相続人全員が「どの評価方法を採用するのか」を理解し、納得することです。
情報が共有されないまま話を進めると、不信感から深刻な対立に発展しかねません。
評価額の根拠を丁寧に確認し、早い段階で合意を形成することが、トラブル防止の第一歩です。
それでも話し合いが難しい場合には、専門家の力を借りることを強くおすすめします。
不動産鑑定士は公正な価格を算出し、税理士は相続税を適正に申告できます。司法書士は登記をスムーズに進め、弁護士は相続人の代理として交渉や調停に臨むことができます。
特に相続人同士の関係がこじれている場合や、調停・裁判に発展しそうなケースでは、弁護士への早めの相談が不可欠です。
不動産相続は「知識」と「準備」と「専門家の関与」で円満に解決できます。
もし今まさに評価や分割で迷っているなら、一人で抱え込まず、専門家へ相談してください。
それが家族の争いを防ぎ、安心できる未来を築くための最良の一歩となります。


 お問い合わせ
お問い合わせ