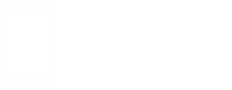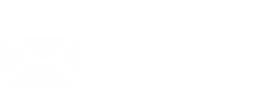- 最終更新:
不動産を遺産分割する4つの方法とは?円満な分割のコツと流れを解説
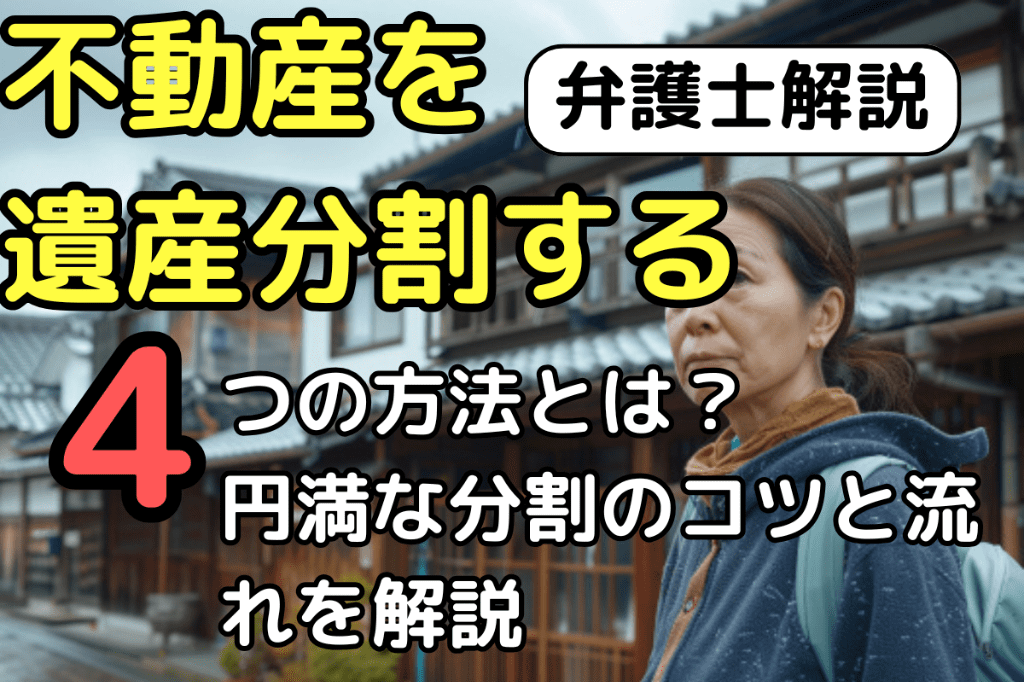
はじめに
親がなくなり悲しむ間もなく、死後事務手続きが山積み。
さらに、遺産に不動産があり、他の相続人から不動産をどうするの?と問い合わせがきている。
とても大変な状況かと思います。
この記事では、不動産を相続した場合にどのように分割すればいいのか不動産相続の全体像と手続きを解説します。
【この記事でわかること】
- 不動産の遺産分割の特徴は、
- 現金のように分けにくく、相続で特に揉めやすい理由
- 遺言書がある場合とない場合での対応の違い
- 不動産を分ける4つの方法
- 現物分割(そのまま相続)
- 代償分割(代償金の支払い)
- 換価分割(売却して現金で分ける)
- 共有分割(共有名義にする)
- 円満な不動産分割の4つのコツ
- オープンな情報共有と冷静な話し合い
- 感情的にならずに冷静に話し合う
- 「言った・言わない」を防ぐ記録化
- 弁護士など専門家の関与の有効性
- 遺産分割から相続登記までの流れ
- 遺産分割協議書の作成
- 相続登記
- 相続税申告
- 準確定申告
- いずれも期限に注意する
- 協議がまとまらない場合の調停・審判
- 2024年4月からの相続登記義務化され、不動産名義変更が必須になったこと
とその申請手続きの概要と必要書類 - 専門家の役割と依頼するメリット
・司法書士、税理士、弁護士の役割の違い
・専門家に依頼することでトラブル防止・手間削減が可 - 将来のための遺言書作成の重要性
・エンディングノートだけでは不十分
・公正証書遺言や自筆証書遺言書保管制度を活用すべき理由
目次
1.不動産の遺産分割とは?
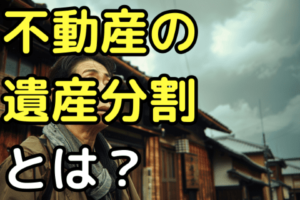
遺産分割とは、被相続人(亡くなった親など)が残してくれた財産(遺産)を、相続人ら(子や孫)で分けることをいいます。
そして、相続人らが遺産の分け方について話し合うことを「遺産分割協議」と言います。
遺産分割協議は、原則として、相続人全員の合意が必要です。
1)不動産の相続はなぜ揉めやすい?
遺産に不動産があった場合は、大小の差はありますが揉めることが多く、すんなり終わることは多くありません。
なぜなら、不動産は、その名のとおり動かすことはできない資産であり、現金のように厳密に分けるのが難しいためです。
また、同じものが他にはないという特徴があるため、時価が算出しづらく、ケーキのように切ってまったく同じものを複数作ることもできません。
不動産の性質上、物理的にも経済的にも、「公平に」分けるということがとても難しいため、揉めやすいという背景があります。
2)遺言書がある場合とない場合の違い
遺言書があり、「誰に何をあげるか」 明確に記載してくれている場合は、その内容に従えば問題ありません。
例えば、不動産は長男に相続させるという記載があれば、不動産を分割する必要がなくなります。
ですが、遺言書があっても、誰に何をあげるのか具体的な記載がない、特定の人に遺産が偏りすぎて、遺留分が生じているという場合は、遺言書に従えばOKというわけにはいきません。
この場合は、遺言書がない場合と同じく、話し合いで不動産の分割、処分をしなければなりません。
2.不動産を遺産分割する4つの方法
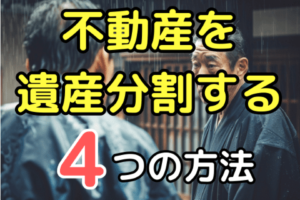
不動産を遺産分割する具体的な方法は次の4つになります。
1)【現物分割】:不動産をそのまま誰かが相続する
現物分割とは、不動産を誰か一人が相続する、土地を分筆して区分けして各相続人が相続することをいいます。
一人の相続人が不動産全部を相続する場合は、不動産を分けることはありません。
この場合、不動産を相続する人は他の遺産を相続しなかったり、他の相続人が預貯金を多くもらうことで帳尻を合わせるケースが多いです。
不動産自体はそのまま残せるため、実務としてもこの現物分割がもっとも多くみられます。
ですが、その不動産をいくらと評価するかということで、相続人間でもめることになります。
不動産をもらう人は不動産価格を安く評価したいし、もらわない人は不動産価格を高く評価したいとなるからです。
2)【代償分割】:不動産を相続した人が他の相続人に現金を支払う
代償分割とは、不動産を相続人した人が、その不動産相当額を他の相続人に支払うことをいいます。
例えば、評価額3,000万円の不動産を、3人で単純に3分の1ずつに分けるケースで考えてみましょう。
長男が不動産をそのまま相続したら、兄弟2人にそれぞれ1,000万円ずつのお金を「代償金」として支払います。
現物分割との違いは、遺産のうち不動産が占める割合が多いため、不動産を誰かが相続すると他の相続人がもらう遺産がない場合にとる分割方法であることです。
この場合も、不動産を分けることはありませんが、その不動産がいくらであるかということで揉めることになります。
不動産をもらう人は不動産価格を安く評価したい、もらわない人は不動産価格を高く評価したいとなるからです。
3)【換価分割】:不動産を売却して現金で分ける
換価分割とは、不動産を相続人以外の第三者に売却して現金で分けることをいいます。
この方法がもっとも揉めない方法になります。
なぜなら、不動産は現金化されており同じ額に分けることができること、第三者に売るため相続人全員が売主という同一の立場となるから不動産価格で相続人間で争わないことからです。
ただし、相続した不動産を売却したということになるため、相続税とは別に売却によって譲渡益があるときは所得税がかかることに注意が必要です。
4)【共有分割】:不動産を共有名義にする
共有分割とは、その不動産を一部または全員の相続人で共有することをいいます。
共有とは、一つのものを複数人で所有することをいいます。
不動産を分けることもなく、価格評価することもないため、遺産分割という観点ではもめることはすくないです。
ですが、これは今決めるべきことを後回しにしているにすぎませんので、おすすめできる方法ではありません。
つまり、共有している人と利害対立することなく持ち続けるということはあまりないですし、仮に自分の代では出来ても自分の相続人になるとそうはいきません。
一般的には、将来に揉め事を持ち越すことになり、時間が経ったことで当時のこと知らない、疎遠な人と協議するという、より難易度の高い協議をすることになります。
3.トラブルを避け「円満な遺産分割」にする4つのコツ
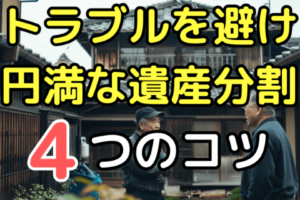
相続人同士、兄弟間でのトラブルを避けるためのコツをお伝えします。
1)オープンなコミュニケーションがとにかく重要
揉めるきっかけになるのは、「不公平」です。
相続人の誰かが「あれこれって不公平でないのか?」と思った瞬間からトラブルになってしまいます。
不公平と思うか思わないかは相手の考えですから、自分が公平だと思うこととは関係ありません。
細かいことであっても出来る限りすべてを包み隠さず伝えることです。
2)感情的にならず、冷静に話し合う
ある相続人がこれって不公平ではないかということを言ってきます。必ず。
自分がどう考えても公平だと思っていると腹が立ってしまいます。
ですが、絶対に感情的にならず、冷静に話し合いましょう。
相手は何か事実を知らないか勘違いしているかもしれません。
両方が感情的になったらもう後戻りが難しいトラブルになってしまいます。
3)「言った、言わない」を防ぐメモ
話し合った過程などをすべてメモして、相手に送ります。
メモするだけでなく相手に送ることが大切です。
相手だけでなく全相続人に送るのがより良いです。
言った言わない、今どのような話し合いをしているかを全当事者が認識していることが大切です。
認識の不一致がトラブルの発端となります。
4)弁護士を交えた話し合いを検討
遺産分割協議を弁護士に依頼するとトラブルが起きにくいです。
弁護士は第三者の専門家として、話し合いを進めることが出来ます。
遺産分割の交渉に長けている弁護士であれば、感情的にならずに、話し合いを記録しながら、依頼人の利益を確保します。
4.遺産分割で不動産を相続する際の流れ
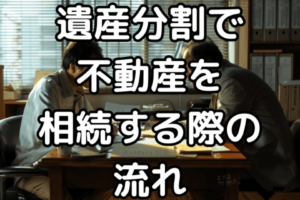
ここまで遺産の「分け方」と「揉めないコツ」を解説してきました。
遺産分割の話し合いが、相続全体流れの中ではどこにあるのかを改めて解説します。
遺産分割で不動産などを相続する際の流れは次の通りです。
- 遺産分割協議をまとめる
- 相続登記を法務局に申請する
- 相続税申告をする(10ケ月以内)
- 準確定申告をする(4ケ月以内)
相続税申告が10ケ月以内なので、相続人が亡くなった時から10ケ月以内に遺産分割協議がまとまるのが理想です。
遺産分割協議がまとまらなくても、10ケ月以内に相続税申告をする必要があることに注意が必要です。
10ケ月以内に相続税申告をしないと、延滞税がかかるだけでなく、様々な特例による相続税の減税が受けられなくなります。
また、被相続人が確定申告が必要な方である場合は、相続人が亡くなった時から4ケ月以内に準確定申告をする必要があります。
また、4ケ月以内に準確定申告をしないと延滞税がかかってしまいます。
1)話がまとまったら「遺産分割協議書」を作成する
遺産分割の方法を決めて、相続人の間で合意がとれたら、必ず「遺産分割協議書」という形で残しましょう。
遺産分割協議書は相続登記などの手続きにも必要ですし、あとで話が蒸し返されて「言った・言わない」の揉め事になるのを防ぐのにも役立ちます。
遺産分割協議書の書式例を掲載します。
遺産分割協議書(案)
本籍 東京都港区〇〇番
最後の住所 東京都港区
被 相 続 人 X(令和〇年〇月〇日死亡)
上記の者の相続人全員は、被相続人の遺産について協議を行い、次の通り分割することに同意した。
1.相続人Aは次の遺産を取得する。
【土地】
不動産番号 00000000
所 在 港区〇
地 番 〇番〇
地 目 宅地
地 積 80.00㎡
【建物】
不動産番号 00000000
所 在 港区〇
家 屋 番 号 〇番〇
種 類 居宅・車庫
構 造 木造合金メッキ鋼板ぶき陸屋根2階建
床 面 積 1階 50.11㎡
2階 50.00㎡
2.相続人Bは次の遺産を取得する。
【現金】 金10,000,000円
【預貯金】
〇銀行〇支店 普通預金 口座番号00000000
〇銀行〇支店 定期預金 口座番号00000000
【株式】
〇株式会社 普通株式 〇株
3.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人Aがこれを取得する。
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。
令和〇年〇月〇日
【相続人Aの署名押印】
住所
氏名 実印
【相続人Bの署名押印】
住所
氏名 実印
行政は電子化が進み押印を廃止しており、実印の押印、署名が必要?と思うかもしれません。
ですが、署名、実印による押印はしておいた方が良いでしょう。
なぜなら、現時点(令和7年)において、かかる制度が、行政、金融機関と一律ではないからです。
遺産分割協議書は、銀行口座、証券口座のある金融機関に、不動産を管轄する法務局に提出します。
そしてこれらの機関によって、署名がないからだめ、実印がないからだめ、不動産の所在等がないからだめということがあります。
わざわざこの機関の手続きのためだけに、別の遺産分割協議書を作り直す羽目になるのは、無駄ですしトラブルを起こします。
2)話し合いで決まらなければ遺産分割調停・審判で決定
遺産分割協議でまとまらない場合は、裁判手続きである遺産分割調停に進むことになります。
遺産分割調停とは裁判所が間に入って当事者同士で話し合いをすることです。
遺産分割調停でもまとまらない場合は、遺産分割審判となります。
遺産分割審判とは、話し合いではなく裁判所が遺産分割の方法を決定することをいいます。
| 項目 | 遺産分割調停 | 遺産分割審判 |
|---|---|---|
| 手続き | 当事者全員が合意した内容で分ける | 裁判所が分割方法を決定する |
| 調停委員の関与 | あり(調停委員が間に入って調整) | なし(家庭裁判所の裁判官が判断) |
| 主な目的 | 裁判所が仲介しつつ、話し合いで合意を目指す | 調停で合意できなかった場合に、裁判所が決定 |
| 当事者の出席 | 原則、全員の出席が必要 | 一方の出席でもOK(書面でも可) |
遺産分割調停は、あくまでも話合いですから、遺産分割協議の延長です。
ですが、裁判所が間に入って妥当な結論へ導くお手伝いをしてくれるため、相続人らの納得が得やすく協議が進みます。
遺産分割調停でもまとまらない場合は、自動的に審判に移行します。
審判は、皆さんが裁判といえばというイメージをもたれているとおりですが、決まるまでそれほど時間を要しません。
また、審判に移行しても、裁判所が間に入って話し合いでの解決が模索されるでしょう。
話し合いでの解決が無理そうだとなれば、裁判所が遺産分割の方法を決めることになります。
5.2024年4月義務化!「相続登記」の申請と必要書類
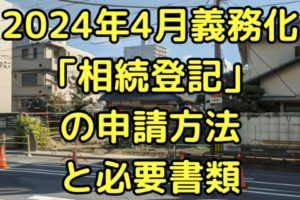
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
これまでは、遺産相続の登記手続きがされないまま放置されていることが少なくありませんでした。
遺産分割をそもそもしなかったり、遺産分割協議書を作っておらず、相続登記をしないということもありました。
ですが、現在は「相続登記」の手続きが義務化されており、避けては通れません。そこで、相続登記について解説します。
1)相続登記とは不動産の名義変更
相続登記とは、不動産の名義人を変更することです。
不動産は登記という制度によって権利関係が公開されています。
例えば、ご自宅を所有されている場合、土地と建物の所有権が被相続人の名前となっています。
これを相続によって引き継いだ旨を登記するのです。
なお、不動産を相続してから3年以内に相続登記をしなければ、10万円以下の過料となります。
過料というペナルティがあるだけでなく、これまでおつたえしたとおりトラブルを防止するために相続登記は速やかに申請してください。
昔と異なり、必要書類の取得、申請書の作成などかなり楽になりましたから、ご自分での対応も比較的簡単です。
相続登記の方法について解説します。
2)相続登記の具体的な申請手順:自分でもできる
相続登記の申請手順は次の通りです。
- 被相続人が亡くなる
- 戸籍、原戸籍を取得
- 遺産分割協議をまとめる
- 登記申請書の作成
- 法務局に提出
- 登記が完了して権利証(登記識別情報)をうけとる
3)戸籍の取得
戸籍とは、出生から死亡までの身分関係をまとめる制度です。
戸籍は、本籍地の役所において管理されており、本籍地の役所において取得します。
本籍地を変更した場合は、変更後の身分関係については、新しい本籍地が管理しています。
相続登記においては、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要となるため、被相続人の全本籍地において戸籍を取得する必要があります。
なぜなら、相続登記においては、相続人の確定が必要なところ、子どもや養子をすべて確認する必要があるからです。
なお、本籍地ではない役所においても戸籍を取得することができつつありますので、お近くの役所が対応しているか確認してください。
4)相続登記申請書の作成と提出
相続登記申請書を作成し、必要書類を添付して、法務局に提出します。
必要書類は、主に戸籍謄本(相続人の出生から死亡まで、相続人の現在のもの)、住民票の写し(不動産を相続する人のもの)、遺産分割協議書(印鑑証明書付き)です。
申請する法務局は、その不動産を管轄する法務局です。
どこの法務局が管轄するかは、法務局ホームページで確認ください。
また、相続登記申請書記載例は、法務局のホームページで確認ください。
なお、相続登記の流れについても、、法務省民事局がとてもわかりやすく解説していますので、参考にして下さい。
5)手続きを簡略化!「法定相続情報証明制度」を活用
法定相続情報証明制度とは相続人から相続関係を一覧に表した図と戸除籍謄本等を登記所に提出し、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するものです(平成29年5月創設)。
この制度のメリットは、相続人が誰であるかの公的証明書を無料で複数枚とれることです。
相続の手続きにおいて、遺産不動産が複数の管轄にまたがっている、遺産の銀行口座、証券口座が複数の金融機関にある際に、各機関に相続人が誰であるかの証明を出さなければなりません。
戸籍謄本で証明するとなると、原本を要求されることが多く、出生から死亡までの戸籍謄本を複数通取得することになります。
手間がかかる上に、戸籍謄本は1通450円、原戸籍は1通750円、除籍は1通450円かかりますから、複数通に及んだりすると合計で結構な費用になってしまいます。
これらの手間を一度で終わらせることが出来ます。
詳しくは、法務局のホームページをご覧ください。
6.「不動産相続」の困ったを解決する専門家
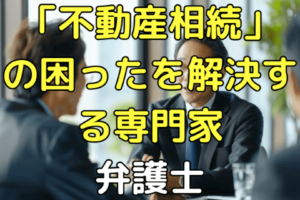
手間がかかりすぎる、交渉が困難、トラブルになってしまったなど専門家を使うことを検討ください。
どのタイミングでどの専門家に相談するのがいいのかを解説します。
1)遺産分割がまとまっている
遺産分割がすんなりまとまったとすると、残すは手続きのみです
相続登記は司法書士さん、相続税申告、準確定申告申告は税理士さんに相談します。
いずれの手続きも結構な手間がかかりますが、自分ですることも可能です。
相続登記手続きは5章を確認いただき、法務局でも相談にのってもらえるので、これらを活用ください。
税務申告手続きは、小規模宅地等の特例など税額を減らせる特例を見逃さないように、税務署で相談にのってもらいましょう。
不動産を賠償して相続するような場合には、その地域に強い不動産売買仲介会社に相談するのがいいでしょう。
2)遺産分割がまとまらない、話し合いが難しい、交渉したくない
遺産分割がまとまらない、話し合いが難しい、交渉をしたくない場合は、あなたに代わって交渉ができる唯一の専門家である弁護士に依頼するか検討してください。
遺産分割は、遺産の多寡に関わらずもめる傾向にあります。
相続人間が全く同じように親と接してきたということはありませんから、多かれ少なかれ不公平があるからです。
様々な手続きの面倒くささなどを加味して、始めから弁護士に依頼するのも一案です。
なお、弊所では、弁護士だけでなく税理士、司法書士も所属しており、一連の流れでご相談ご依頼頂けます。
3)各専門家の役割、メリットについて
各専門家の役割を解説します。
【司法書士】:登記の専門家で相続登記による名義変更です。
【税理士】:税務申告の専門家で相続税申告です。
【弁護士】:法務全般の専門家で交渉ができる唯一の専門家です。
どの専門家であっても相続について専門的に扱っている専門家を選んでください。
相談無料というところもありますので、相談してみてから選んでみるのもいいでしょう。
専門家に依頼するメリットは、大きく3つで、適正な手続きができる、手間を大きく削減できる、交渉の代理を任せられることです。
ご自身の状況に応じて上手に専門家を使い分けてください。
4)相続人自身で手続きを進める場合の注意点と限界
専門家に依頼すると費用がかかるということがデメリットです。
ですから、出来る限り依頼しないという判断もあるでしょう。
ですが、専門家に依頼しないことで、大きく損をするということもあります。
例えば、交渉を自分でやり切ろうとして、相続人間のトラブルが大きくなり、もう二度と顔を合わすことがなくなってしまった兄弟をたくさん見てきました。
そこまでして、納得がいく結果になったのであれば良いかもしれませんが、そうではないことが大半です。
また、自分で相続税申告をして税金を払い過ぎた、重加算税などのペナルティを取られたなどとなっては大変です。
ご自身の仕事においても全くの素人が突然やってきてできるのだろうかと考えてみてください。
7.今後のために!遺言書のすすめ
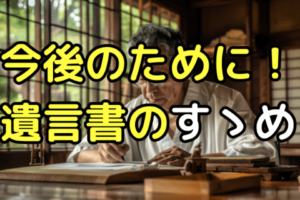
終活などの言葉がはやり、金融機関などを中心にエンディングノートなどを書くことを進める会社が増えました。
ですが、エンディングノートを書くだけでは不十分です。
エンディングノートは、金融機関が財産を把握して営業に繋げたいという意図があり、金融機関の勧めでは、エンディングノートを書くだけで終わってしまいます。
ですが、大切なことは、書くだけでなく残すことです。
あなたが亡くなった時に、相続人にあなたの考えが伝わらないとエンディングノートを書く意味がありません。
自分のために書くエンディングノートはあっていいとも思うのですが、もう一歩進んでください。
亡くなった時にみんなに知ってもらえるようにしてください。
そこで、利用したいのが、遺言書を書いて、公正証書にするか自筆証書遺言書保管制度を利用することです。
参考:日本公証人連合会ホームページ(公正証書遺言)
参考:法務省ホームページ(自筆証書遺言書保管制度)
これらの制度を使うことで、相続人に遺言書を見てもらうことができるようになります。
まとめ
不動産相続における遺産分割は、相続全体の中でも特にトラブルが起きやすい分野です。不動産は現金のように簡単に分けられず、評価額や分け方をめぐって相続人同士の意見が対立しやすい資産です。そのため、不動産相続を円満に進めるためには、遺産分割の方法や流れを正しく理解しておくことが重要です。
不動産を遺産分割する方法には、主に4つあります。①誰かがそのまま取得する「現物分割」、②取得者が他の相続人に代償金を支払う「代償分割」、③不動産を売却して現金で分ける「換価分割」、④共有名義とする「共有分割」です。なかでも「共有分割」は将来のトラブルを先送りにしてしまう可能性が高く、不動産相続を複雑化させるリスクがあります。
円滑な遺産分割のためには、相続人全員が不公平感を抱かないことが大切です。情報をオープンに共有し、冷静に話し合いを行い、記録を残すことが基本となります。また、不動産相続の場面では弁護士など専門家の関与も有効です。第三者が入ることで感情的な衝突を避け、スムーズに遺産分割を進められる可能性が高まります。
不動産相続の手続きの流れは、遺産分割協議の合意、遺産分割協議書の作成、相続登記、相続税申告というステップが基本です。特に相続税申告は10か月以内、準確定申告は4か月以内に行う必要があり、期限を過ぎると延滞税や減税特例の喪失といった不利益が生じます。さらに2024年4月からは相続登記が義務化されており、不動産を相続した場合は3年以内に登記しなければ過料の対象となります。
こうした事情から、不動産相続はできる限り早めに遺産分割をまとめることが望ましいです。協議がスムーズに進めば司法書士や税理士に依頼して手続きを進められますが、相続人間で話し合いが難しい場合は、交渉の専門家である弁護士に依頼することが効果的です。
また、将来の不動産相続を円滑に進めるためには、遺言書を残すことが何より大切です。エンディングノートだけでは法的効力がなく、相続人の混乱を招きかねません。公正証書遺言や自筆証書遺言保管制度を活用することで、遺産分割の方針を明確に示し、家族のトラブルを未然に防ぐことができます。
不動産相続の遺産分割は、家族関係や財産を守る大切なプロセスです。この記事が不動産を相続した方の遺産分割にお役に立てると幸いです。


 お問い合わせ
お問い合わせ