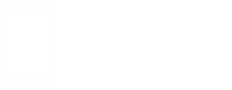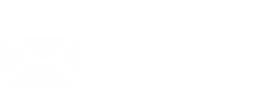- 最終更新:
遺産分割協議とは?やり方と協議書作成の全手順
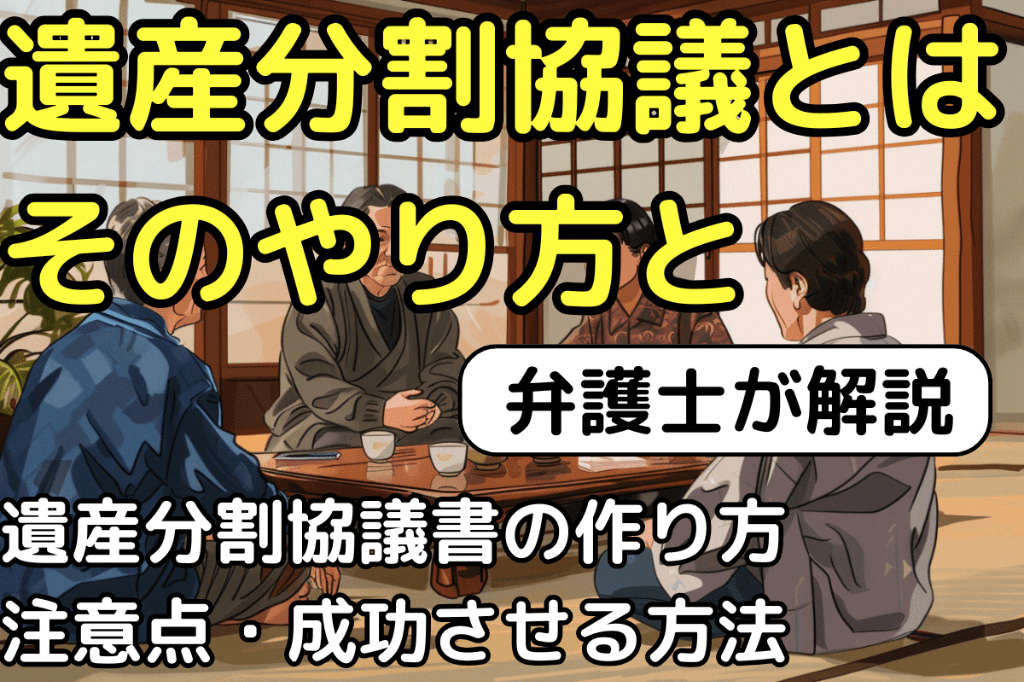
はじめに
親や配偶者が亡くなったとき、避けて通れないのが相続手続きです。
不動産や預貯金などの遺産を分ける 「遺産分割協議」をすることになります。
そして、協議内容を遺産分割協議書にまとめることになります。
しかし、作成方法を誤るとやり直しになったり、後々相続人同士でトラブルになったりするケースも少なくありません。
本記事では、遺産分割協議や遺産分割協議書について、初めて相続に直面した方でも流れや手続きが理解できるように解説しています。
【この記事でわかること】
- 遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合うこと
- 遺産分割協議の流れは、相続人確定、財産調査、協議、書面化をする
- 遺産分割協議書の作成方法(書き方のポイントと必要書類)
- 不動産登記や銀行手続きにおける提出方法(法務局・金融機関での扱い)
- よくあるトラブル事例と防止策(合意できない場合や記載漏れのリスク)
- 弁護士に依頼するメリット(調整・代理・トラブル防止の実務サポート)
不動産の遺産分割の方法について詳しく知りたい方は、「不動産を遺産分割する4つの方法とは?円満な分割のコツと流れを解説」をご覧ください。
目次
1.遺産分割協議書とは?

遺産分割協議とは、相続人(全員)で遺産をどのように分けるか話し合うことをいいます。
そして、遺産分割協議書とは、相続人全員が合意した内容を証拠として残す書面をいいます。
被相続人(亡くなった方)が残した財産を遺産といい、遺産には、不動産・預貯金・株式・自動車などさまざまな種類の財産があります。
被相続人が遺言書を残していて、その遺言書において、すべての遺産を誰に相続させるかが決まっているとすると、遺産分割協議は必要ありません。
しかし、被相続人が遺言書を残していなければ、遺産を誰が引き継ぐのかを決めるために、遺産分割協議をする必要があります。
そして、遺産分割協議がまとまると、それを書面化して形に残します。
遺産分割協議書とは、その書面化して形に残したものをいいます。
2.遺産分割協議の進め方とその後の手続き
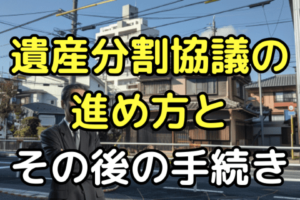
遺産分割協議はどのように進めたらいいのか、流れや手順について、具体的に解説します。
1)ステップ1:相続人の確定
まず初めにすることは、誰が相続人なのか、相続人全員を確定させることです。
そのために、被相続人の出生から死亡までの戸籍・原戸籍等を収集します。
戸籍とは、出生から死亡までの身分関係を公証する公簿です。
戸籍は、被相続人の本籍地の役所で取得することができます。
本籍地を変更していた場合は、その変更前の本籍地にて戸籍を取得する必要があります。
昨今、行政のデジタル化に伴い、本籍地以外の役所でも戸籍を取得できるように制度変更が進められています。
本籍地以外の戸籍を取得できるかどうかは、最寄りの役所にご確認ください。
なお、相続人全員が分かりきっているからといって、被相続人の戸籍取得を省略しないでください。
実は、自分の知らない異母兄弟がいたということが稀にあります。
そのような場合は、遺産分割協議をやり直す羽目になります。
また、今後の手続きにおいて、被相続人の出生から死亡までの戸籍は必要となります。
いずれにしても、必要となる書類ですから、省略せずに取得してください。
2)ステップ2:相続財産の調査
次に、相続財産の調査(遺産の内容を確認すること)が必要です。
遺産の内容すべてを明らかにしないと、誰にどの財産を相続させるのかを決められません。
調査の方法は、財産の種類によって異なります。
- 不動産
- 毎年4月頃に届く固定資産税納税通知書を確認する
- 不動産がある役場で名寄帳を取得する
- 預貯金
- 通帳などを確認する
- 金融機関から残高証明書を取得する
- どこの銀行にあるかがわからない場合は、各銀行の本部に全店照会をする
- 株式
- 口座などを確認する
- どこにあるかわからない場合は、証券保管振替機構に照会する
- 生命保険
- 保険証券の確認
- 生命保険協会に照会する
- 車
- 車検証を探す
- 自動車税の納税通知書を確認する
これらの方法を用いて、遺産の内容、どのような財産がどこにどれだけあるのかを確認します。
3)ステップ3:相続人全員で話し合う
遺産分割協議、つまり相続人全員で誰がどの遺産を受け取るかを話し合います。
法定相続分を基準にして、家族の慣行、これまでの経緯を加味して、相続人が公平になるように分けます。
法定相続分とは、民法の定めによるものです。
例えば、両親と子ども2人の家族で、父親が亡くなったとします。
この場合は、母親が二分の一、子どもがそれぞれ四分の一となります。
ここで難しいのが、公平に分けるということです。
相続人が兄弟だとすると、親は、兄弟に公平に愛情を注いでいるでしょう。
ですが、愛情を注がれた側の受け止め方は被相続人それぞれ異なります。
また、親の資力や考え方にも変遷があるため、子供たちに対して、平等に援助することは困難です。
例えば、次のような違いがあるでしょう。
弟は私立の学校に通った、兄は家を買うときに援助してもらった、姉は一緒に住んで生活費を出してもらっている、兄の子供への学費援助をしているなどです。
このような相続人のそれぞれの思いをうまくまとめながら、遺産分割をまとめていきます。
現金、株など有価証券以外はそのものを分割することが難しく、遺産の分割が難しくなります。
不動産の分割方法は、「売却して分ける(換価分割)」「1人が取得して代償金を支払う(代償分割)」など選択肢があります。
不動産の遺産分割の他の方法(現物分割、代償分割、換価分割)について詳しく知りたい方は、「不動産を遺産分割する4つの方法とは?円満な分割のコツと流れを解説」をご覧ください。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。
全員の利益調整と感情調整をしながら、合意させていきましょう。
4)ステップ4:遺産分割協議書を作成
遺産分割協議を何とかまとめることが出来たら、それを書面化しておきましょう。
合意した内容を書面化して、言った言わないなどのトラブルを防止します。
詳しくは、次の3章で解説します。
5)ステップ5:その後の各種手続き
遺産分割協議がまとまった後は、まとまった協議内容どおり実行する手続きが必要です。
また、相続税申告、準確定申告が必要です。
詳しくは、4章で解説しますので、ぜひご覧ください。
3.遺産分割協議書の作成方法
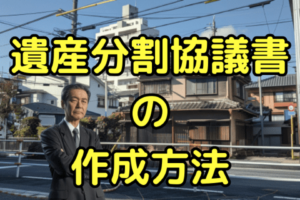
遺産分割協議書には次の基本的ルールがあります。
- 相続人全員が合意する
- 1人でも参加していない、相続人全員でないものを加えた場合は、その遺産分割協議は無効となります。
- 相続人全員が署名し、実印で押印する
- 電子化をすすめ、押印を省略しはじめていますが、現時点ではすべての手続きで押印が省略されていません
- 各相続人の印鑑証明書を添付する
- 押印したものがその時点において実印登録されているものか確認が必要です
- 財産を漏れなく記載し分割すること
- 漏れた財産があると、その財産について再度遺産分割協議が必要となってしまいます。
次に、書き方のポイントをお伝えします。
- 不動産について
- 「所在」「地番」「地目」「地積」など登記事項証明書どおりに正確に記載します。
- 預貯金
- 金融機関名・支店名・口座番号まで明記する。
- 有価証券
- 金融機関名・支店名・口座番号・銘柄・株数まで明記する。
遺産分割協議書の記載例を以下に示します。
あくまで一般例 であり、ケースに応じて修正が必要です。
遺産分割協議書(例)
本 籍 東京都港区・・・・
最後の住所 大阪府高槻市・・・
被 相 続 人 X (平成何年何月何日死亡)
上記の者の相続人全員は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次のとおり分割することに同意した。
1.相続人Aは次の遺産を取得する。
【土地】
所 在 ・・・
地 番 ・・・
地 目 宅地
地 積 120.00㎡
【建物】
所 在 ・・・
家屋番号 ・・・
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階 70.00㎡
2階 72.00㎡
2.相続人Bは次の遺産を取得する。
【現金】 金2,000,000円
【預貯金】
・・銀行・・支店 普通預金 口座番号0000000
・・銀行・・支店 定期預金 口座番号0000000
【株式】
株式会社・・ 普通株式 100株
3.Aは、第1項記載の遺産を取得する代償として、Cに対して、令和〇年〇月〇日までに、30,000,000円を支払う。
4.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人Aが取得する。
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を3通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。
平成何年何月何日
【相続人Aの署名押印】
住所
氏名 実印
【相続人Bの署名押印】
住所
氏名 実印
【相続人Cの署名押印】
住所
氏名 実印
4.その後の手続きと遺産分割協議書が必要となる場面
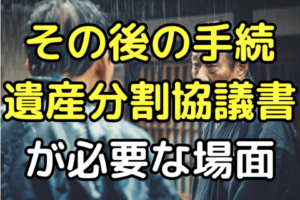
遺産分割協議がまとまり、遺産分割協議書を作成できれば、その後の手続きに移ります。
なお、税務手続きについては、被相続人の死亡から10ヶ月または4ヶ月以内といった期限がありますから、遺産分割協議がまとまっていなくても、期限までに申告と納税をしなくてはなりません。
1)不動産登記の申請
遺産分割に不動産が含まれている場合は、遺産分割協議で誰が相続するかを決めて、相続による所有権移転登記をする必要があります。
不動産登記に必要な書類は以下のとおりです
- 被相続人の戸籍一式
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人の住民票
登記は、法務局にあるひな形を利用して、必要事項を記載し、添付書面を添えて、法務局に申請します。
これらの方法は、法務局が出している登記申請手続きのご案内に詳しく記載されています。
また、どうしてもわからない場合は法務局が相談にのってくれます。
自分たちでやるのは面倒くさいという方は、司法書士に任せましょう。
なお、法務局に遺産分割協議書を添付する必要があります。
遺産分割協議書にはすべての遺産の分割方法が記載されていますが、法務局に必要なのは登記をする不動産の記載のみです。
そこで、法務局用として不動産だけを記載した遺産分割協議書を作るということが実務的には多くなされています。
2)銀行・証券会社での相続手続き
遺産に銀行・証券口座がある場合には、解約などの手続きが必要となります。
相続の手続きで必要な書類は以下のとおりです
- 被相続人の戸籍一式
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書
- 通帳、キャッシュカードなど
これらの書類は、コピー不可としている金融機関が多く、金融機関ごとに原本が求められます。
戸籍一式は、取得に時間もお金もかかりますし、何通もとるというのはお金がかかります。
そこで、法務局による法定相続情報一覧図を作成してもらうと、無料で何度でも戸籍一式の代わりになるものを出してもらえます。
遺産に金融機関が複数ある場合には、ぜひ法定相続情報一覧図をご利用ください。
法定相続情報制度は、詳しく法務局のホームページで説明があります。
3)税務申告
相続により必要となる税務申告は、相続税申告、準確定申告です。
準確定申告とは、亡くなった方の確定申告のことで、相続開始から4ケ月以内に申告し、納税する必要があります。
相続税申告とは、亡くなった方から財産を引き継いだことで生じる所得にかかる税金の申告であり、相続開始から10ケ月以内に申告し納税する必要があります。
いずれも必ず必要ということではありません。
また、税金の計算を誤って多く申告納税したとしても、税務署が気付いて返金してくれることはありません。
自分で過大納付したとして還付を申告する必要があります。
また、少ない申告をすると、過少申告加算税、重加算税などで不足分以上の納税を強いられます。
ですから、税金計算は多くも少なくも間違えないようにしないといけません。
そこで、税務署に相談にいって、申告書を書き、適正額を納税することをおすすめします。
自分で対応が面倒くさい、土地がたくさんあって大変という場合は、税理士に相談することもおすすめです。
5.遺産分割協議書をめぐるトラブルとその対応策
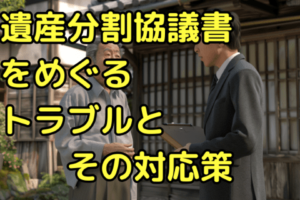
遺産分割をめぐるよくあるトラブルとその対応策をお伝えします。
1)親から家の頭金などで多額の贈与がある
家を買うタイミングで親の資力があれば援助してもらうというのはよくあることです。
しかし、兄弟がいるときに全員平等に援助がもらえるかというとなかなかそうではありません。
その場合に、法定相続分での遺産分割は適切ではないという意見が出てきます。
また、援助を受けた相続人が、援助を受けていない、少額であるなどの反論があるなどして、協議がまとまりません。
贈与の証拠をあつめ相続人間の公平性を保つように話を進めて行きましょう。
それでもまとまらないという場合は遺産分割調停を申し立てましょう。
2)相続人の一人が親と長年同居していた
相続人の一人が親と長年同居していた場合にもよくトラブルになります。
というのも、同居していた相続人は、親の面倒を見ていたのであるから、他の相続人より負担が重く優遇されるべきであると考えます。
ところが、他の相続人は、当たり前のことだし、なんなら事実上生活費などを支援してもらっているから不公平だと考えます。
このように相続人間の評価が全く逆となっています。
寝たきり介護などの過重な負担があった場合は、業者に依頼する費用分の寄与があったと認められます。
ですが、そのような場合でない限りは、親の面倒を見ていた程度では、他の相続人より優遇されません。
このような説明を当事者がしたとしても、なかなか信用してもらえなかったりします。
そこで、弁護士などに依頼して説明をしてもらう。
または、自分で調べる、チャットGPTなどで調べるように勧めてみるのが良いでしょう。
3)遺産の大半が不動産
遺産の大半が不動産である場合も注意が必要です。
不動産は、その性質上全く同じ複数の不動産に分割することができません。
ですから、不動産を売却して現金に変えて分割する換価分割でない限り、公平な分割がとても難しくなります。
ただでさえ、どれぐらいの割合で分けるのが公平なのかが議論になるところに、不動産の価値が公平であるかという議論が上乗せされてしまいます。
このような状態でもめた場合は、なかなか当事者同士でまとまることは難しいでしょう。
この場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てるのが得策です。
6.弁護士などの専門家の利用とメリット・デメリット
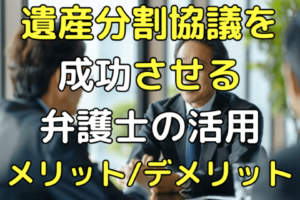
話したことがない人と話しにくい、話を始めたがなかなかうまくまとまらない、まとまる気がしないというときには、専門の弁護士を利用するというのも一つの方法です。
一度でも言い合いになってしまうと信頼関係が壊れてしまい、さらに協議がまとまらなくなってしまいます。
弁護士に依頼するメリットは以下です。
- 弁護士があなたに代わって協議するため、直接他の相続人と話す必要がない
- 遺産分割協議書含め一連手続きを丸投げできる
- 第三者として公平性を検討できる
他方でデメリットは、弁護士費用がかかるということです。
弁護士をいれることで、弁護士費用以上に受け取る遺産が増えるという場合もあります。
詳しくは、遺産分割に強い弁護士にご相談ください。
弊所では、初回相談無料ですので、ぜひご利用ください。
まとめ
遺産分割協議は、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意した内容を「遺産分割協議書」として書面化する重要な手続きです。不動産や預貯金、株式など多様な財産が対象となり、協議書がなければ法務局での相続登記や銀行での口座解約・名義変更ができません。つまり、遺産分割協議書は相続における“必須のカギ”と言えます。
協議のやり方は、①相続人を確定し、②遺産を調査し、③全員で話し合い、④協議書を作成し、⑤登記や金融機関の手続きに進む、という流れです。戸籍収集や財産調査を正確に行うことが前提であり、記載漏れや誤りがあればやり直しが必要になります。特に不動産の記載は登記事項証明書どおりに記載するなど、厳密さが求められます。
一方で、協議がまとまらない場合や相続人の一部が署名・押印しない場合は、家庭裁判所での調停や審判に進まざるを得ません。また、協議内容が偏っていたり財産の記載漏れがあったりすると、後から無効を主張されるリスクもあります。こうしたトラブルを避けるためにも、正確な協議と協議書の作成は不可欠です。
自分で作成することも可能ですが、法務局や銀行で受理されないケース、相続人間での対立に発展するケースは少なくありません。弁護士に依頼すれば、相続人間の調整から協議書作成、不動産登記・銀行手続き・税務対応まで一貫してサポートが受けられ、安心して相続を進められます。
相続は人生で何度も経験するものではなく、戸惑いや不安を抱くのが当然です。遺産分割協議や協議書作成で迷ったら、早めに専門家に相談することが円満かつ迅速な相続解決への第一歩となります。


 お問い合わせ
お問い合わせ