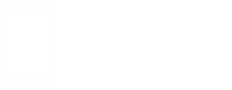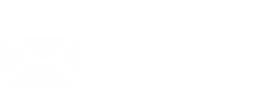- 最終更新:
共有分割とは?手順・遺産分割協議書作成・注意点・成功させる方法!
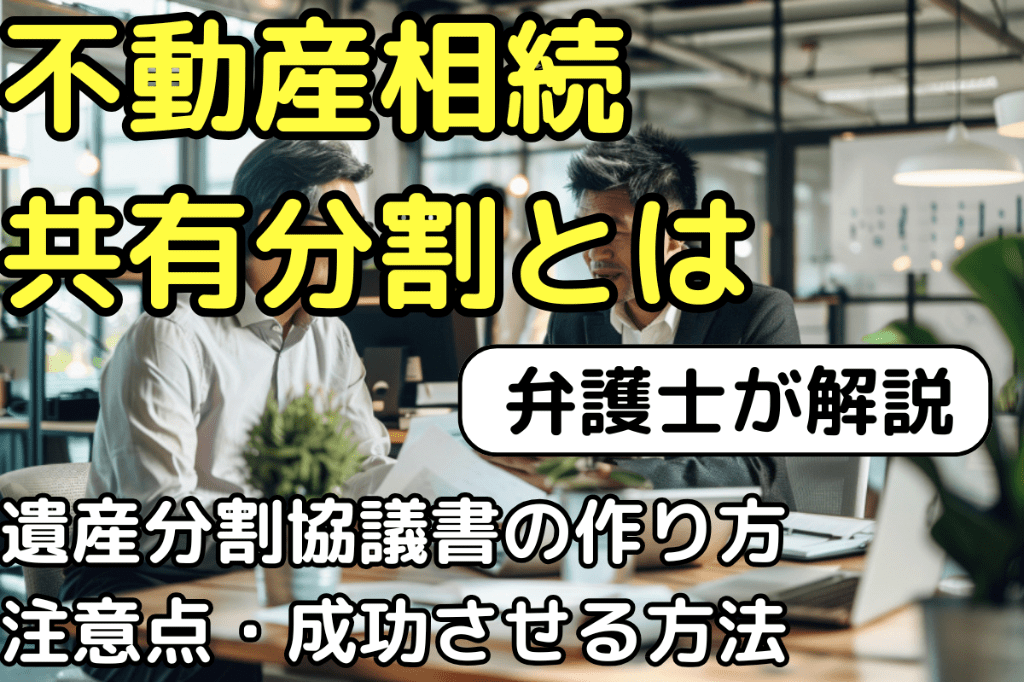
不動産の相続においてよく利用される方法の一つが「共有分割」です。
共有分割とは、複数の相続人が不動産を持分割合に応じて共同で所有する方法をいい、公平性が保たれたり不動産を売却せずに残せたりするメリットがあります。
しかし一方で、維持管理や処分のたびに共有者全員の同意が必要となり、将来の相続でもトラブルが発生しやすいなど多くのデメリットがあるのも事実です。
本記事では、共有分割の仕組みを基礎からわかりやすく解説し、メリットとデメリットを比較検討できるようにしています。
また、現物分割・代償分割・換価分割といった他の不動産遺産分割方法との違いも整理し、どの方法を選ぶべきか判断するための視点を提供します。
共有分割は一見公平な方法に見えても、長期的には不利益を生むケースが多いため、慎重な判断と専門家の助言が欠かせません。
不動産の遺産分割で共有分割を検討している方にとって、後悔しない相続を実現するための実践的な知識を得られる内容です。
【この記事でわかること】
- 共有分割とは、不動産を複数の相続人が持分割合で共有する遺産分割方法であること
- 共有分割には「公平性が保たれる」「不動産を残せる」など4つのメリットがあること
- 一方で、管理や処分に全員の同意が必要となるなど、将来トラブルにつながる6つの大きなデメリットがあること
- 不動産相続では、現物分割・代償分割・換価分割・共有分割の4つの方法があり、状況に応じて選択すべきこと
- 共有分割を選ぶ場合でも、遺産分割協議書の工夫や不分割特約でトラブルを予防できること
- 将来問題が起きた際には、換価分割・代償分割・調停訴訟など5つの方法で共有を解消できること
- 総合的に見ると、共有分割は特段の事情がない限り避けるべき方法であり、弁護士の助言を得ることで最適な遺産分割を実現できること
不動産の遺産分割の他の方法(現物分割、代償分割、換価分割)について詳しく知りたい方は、「不動産を遺産分割する4つの方法とは?円満な分割のコツと流れを解説」をご覧ください。
目次
1.不動産相続の「共有分割」とは何か?
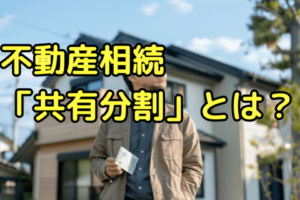
共有分割とは、相続人複数人で不動産を共有する分割方法をいいます。
例えば、相続人3人で不動産の持分を1/3ずつ持つという方法です。
持分とは、一つのものを複数人で共同して所有する場合に、その権利の割合をいいます。
なお、不動産の遺産分割は「共有分割」以外にも方法があります。
【遺産分割の4つの方法】
| 分割方法 | 説明 |
| 現物分割 | 不動産を相続人の1人が受け取る方法 |
| 代償分割 | 不動産を相続人の1人が相続し、他の相続人に代償金を支払う方法 |
| 換価分割 | 不動産を第三者に売却し、その売却代金を相続人で分ける方法 |
| 共有分割 | 不動産を相続人複数の共有にする方法 |
他の方法も含め、遺産分割の方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
関連:「不動産を遺産分割する4つの方法とは?円満な分割のコツと流れを解説」をご覧ください。」
2.共有分割の4つのメリット
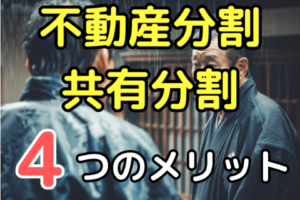
共有分割のメリットは、次の4つです。
①相続人間の公平性が保たれる
相続割合に応じて不動産を共有することになるので、不動産をそのまま全員で共有することができます。
そうすると、各相続人は、持ち分割合に応じて(相続割合に応じて)、その不動産の権利を持ちますから、相続人間の公平性が保たれます。
②不動産を残すことができる
また、不動産を換価のために売却するなどの必要もありませんから、そのまま不動産を残すことができます。
③相続の手続きが比較的簡単
遺産を相続人で複雑に分ける必要がなくなるために、遺産分割協議書の記載も簡潔で手続きも比較的簡潔で簡単です。
④遺産分割協議がまとまりやすい
さらに、公平性が保たれ、手続きが簡易なこともあり、結果として、遺産分割協議がまとまりやすいというメリットもあります。
ですが、原則として、共有分割はお勧めできません。
その理由は、次のデメリットで解説します。
3.共有分割の6つのデメリット
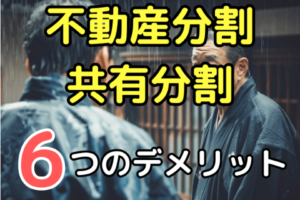
共有分割のデメリットは、次の6つです。
①不動産の維持管理方法でトラブルになる(民法252条)
一つのものを複数人で所有するわけですから、単独で決定することができません。
維持管理については、持分の過半数によって管理者を決定することができ、その管理者が単独で維持管理できます。
誰に維持管理してもらうか、してもらうにしても維持管理の方法について、紛争になるなど、トラブルになりやすいです。
②不動産の変更は全員の同意が必要となる(民法251条)
不動産の変更の場合は、持分の過半数では足りません。
不動産の管理を超えて変更する場合は、所有者全員の同意を得る必要があります。
例えば、その不動産を賃貸している場合に、建物を増改築して、不動産価値を上げて、高い賃料がとりたいと思っても、全所有者の同意が得れないと増改築することができません。
③不動産の処分も全員の同意が必要となる(最高裁昭和42年2月23日)
不動産を処分する場合も、所有者全員の同意を得る必要があります。
例えば、不動産価格が上昇しており、今が売り時だと思って売りたいと思っても、全所有者の同意が得れないと売却することができません。
なお、自分の持分だけを売却するのは自由にできます。
自分の持分を他人に売却することは自由にできますが、持分の売却は買い手が見つかりにくい上に、足元を見られて高値が付きにくいです。
一般的には、不動産全部を売って、持分割合に応じた額を得る方が、持分のみの売却よりも大きくなります。
④共有の解消はかなり面倒くさい
やはり共有は面倒くさいなとおもって、解消したいと思っても、その共有の解消もとても面倒くさいです。
共有という状況は、上記のとおりとても、維持管理、処分に手続きが必要で煩雑です。
とすると、こんな状況はいやだなーと思う人が出てきます。
一人で共有を解消する手続きをとることができ、その解消手続きは全共有者に関わり、かなり面倒です。
詳しくは、6章で解説します。
⑤次の相続でもめる可能性が高い
共有者の一人にさらに相続が発生したら、その持分に対して、相続が発生します。
相続人が一人であれば、遺産分割が不要なため、まだ問題となりにくいです。
ですが、相続人が複数いた場合、その持分をどのように分割するかで話し合いが複雑になり、さらに共有物の変更や解消となると、他の共有者が巻き込まれてしまいます。
⑥小規模宅地の特例の効果をフルでうけられない
税金面でも不利益を被ることが多いです。
小規模宅地の特例という制度があり、相続税評価額を最大8割減してもらえる素敵な特例があります。
これは一人がすべてを引き継ぐ際に最大の効果を発揮します。
共有分割であれば、特定の相続人の持分についてのみ適用にとどまり、減税額は限定的です。
大きな節税効果を発揮するこの特例をフルに生かすことができません。
以上のデメリットとメリットを総合的に考えると、特段の事情がない限り、共有分割は、問題の先送りになるため、避けた方が良いでしょう。
共有であることがベストである状態というのは相当限定され、例えば夫婦で住宅ローンを返している時などくらいではないでしょうか。
4.共有分割の手順と遺産分割協議書の作成方法
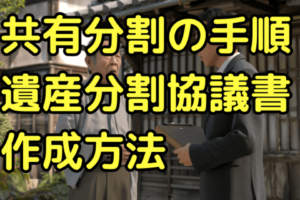
相続の発生から遺産分割終了までの手順を示します。
- 遺言書の確認と相続人の確定
- 遺産分割協議と共有分割の合意形成
- 遺産分割協議書の作成と共有分割の旨を記載する
- 不分割特約を追加検討する
- 不動産の相続登記(不動産名義変更)
不動産を処分したくないが、誰が相続するのか調整できず、代償分割によって代償金を払う資力がない場合に、共有分割にすることが多いです。
また、特にもめることがなく、相続分に応じて共有でいいんではないかと、遺産分割協議がすんなりまとまることもあります。
ですが、お伝えした共有のデメリットや共有の解消の困難さを考慮して検討してください。
なお、当面の共有の解消を防止する、共有持分を他人に売却されにくくするため、共有物不分割特約(民法256条)を付けることも検討しましょう。
この特約の注意点は、5年を超えない期間に限って有効であることと、登記をしないと第三者に対抗できないところです。
遺産分割協議書文言例
1 土地・建物(本件不動産)については、Aが3分の1、Bが3分の1、Cが3分の1の割合で取得する。
2 A、B及びCは、本件不動産について、本合意日から5年間分割しない。
5.共有分割を成功させる弁護士利用
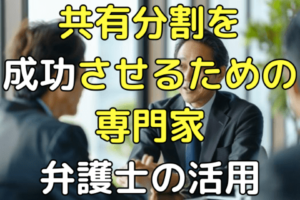
遺産分割協議がまとまりやすい共有分割ではありますが、他の遺産との兼ね合いで上手くまとまらない場合があります。
また、それに加えて、将来を考えた適切な共有分割による遺産分割のアドバイスを受けることが大切です。
さらに、そもそも共有分割でいいのかということも検討してください。
そうだとすると、どのように遺産を分けるべきであるのかということも含めて、弁護士に相談されることをお勧めします。
総合的な公平な遺産の分割に加えて、将来起こりうるトラブルを想定して、今対応しておくことが大切です。
6.将来必要になる?共有を解消する5つの方法
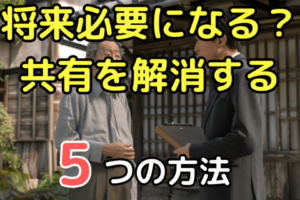
共有状態であることで不具合を感じた場合は、いつでも共有を解消するために、共有者が単独で共有物分割請求をすることができます(民法256)。
共有状態を解消する方法は、次の5つの方法があります。
①換価分割
換価分割とは、不動産を売却して現金を分ける方法です。
全員が売却することに合意できれば、不動産を売却して売却額を持分割合に応じて分けます。
換価分割の方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
遺産分割時における記事ではありますが、分割方法としての換価分割を説明しています。
関連:「換価分割とは?遺産分割協議書の作り方・税金・高く売却する方法を解説」をご覧ください。
②代償分割
代償分割とは、共有者の一人が、他の共有者の持分をすべて買い取るという方法です。
買い取りたい共有者がいて、その資金を確保できる場合にとることができる方法です。
ただし、買い取りたい共有者は安く買いたい、売る共有者は高く売りたいと、立場が相反しているため、容易に話がまとまりにくいです。
なお、資産の譲渡を受けるため、譲渡所得税、不動産取得税など税金がかかる可能性があります。
③自分の持分のみを売却する
自分の持分を他の共有者または第三者に売却することで、自分だけが共有から抜け出すことができます。
ですが、他の共有者は、②で申し上げた利益が相反する立場であるため、まとまりにくい。
持分のみを欲しがる第三者は少なく、買いたたかれてしまうという問題点があります。
なお、資産の譲渡を受けるため、譲渡所得税、不動産取得税など税金がかかる可能性があります。
④現物分割
不動産が土地のみの場合は、土地を分筆(分割)して、各人がその土地を持つという方法があります。
しかし、土地は分筆することができますが、全く同じものに分けることはできません。
そのため、誰がどの部分をとるのかはなかなかまとまらないという問題があります。
なお、現物分割は共有者間で資産の交換があったといえ譲渡所得税が発生しうるのですが、交換による収益の実現があったとは言えないとして、譲渡所得税は生じません。
⑤共有物分割調停・訴訟を提起する
他の共有者に共有解消をお願いしたもののまとまらない場合に、裁判手続きによる共有の解消である共有物分割調停・訴訟という方法があります。
共有物分割調停とは、調停委員が間を取り持って、共有者で話し合いによる解決を模索する方法です。
他方、共有物分割訴訟とは、裁判所に共有物をどのように分割するか決定してもらう訴訟です。
メリットは、共有解消が確実になされること、裁判所の関与の元、共有者間での和解の道が開けることです。
一方、デメリットは、調停・訴訟にかかる時間と費用がかかることです。
調停においては半年から1年、裁判においては1年から2年かかります。
また、訴訟においては、裁判所が判断するため、自分のおもい通りにはならないことです。
まとめ
不動産を相続する際の遺産分割方法の一つに「共有分割」があります。共有分割とは、相続人が不動産を持分割合に応じて共同所有する方法であり、公平性を保ちやすく、不動産を売却せずに残せる点など一定のメリットがあります。また、協議が比較的まとまりやすいという利点もあるため、一見すると便利な方法に思えるかもしれません。
しかし実際には、共有分割には多くのデメリットが存在します。管理や処分の際には共有者全員の同意が必要となり、維持費や修繕費を巡って対立することも少なくありません。さらに、共有者の一人が亡くなった場合にはその持分に再び相続が発生し、関係者が増えることでトラブルが複雑化するリスクも高まります。税制上も「小規模宅地の特例」を最大限活用できないなど、不利益を被る可能性があります。結果として、共有分割は問題の先送りになり、将来の紛争の火種となるケースが多いのです。
そのため、不動産の遺産分割では、現物分割・代償分割・換価分割など、よりシンプルで将来的なトラブルを避けやすい方法を検討することが重要です。やむを得ず共有分割を選ぶ場合でも、遺産分割協議書に不分割特約を盛り込むなど、リスクを最小限に抑える工夫が求められます。
不動産相続は金額も大きく、家族間の関係に深く影響するため、判断を誤ると取り返しがつきません。共有分割を含む遺産分割の方法に迷ったときは、専門的な知識と経験を持つ弁護士に相談することが最も安心です。将来のトラブルを防ぎ、公平で円満な相続を実現するために、ぜひ早めに弁護士へのご相談をご検討ください。


 お問い合わせ
お問い合わせ