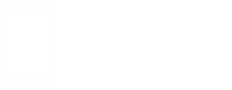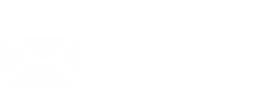- 最終更新:
換価分割とは?遺産分割協議書の作り方・税金・高く売却する方法を解説
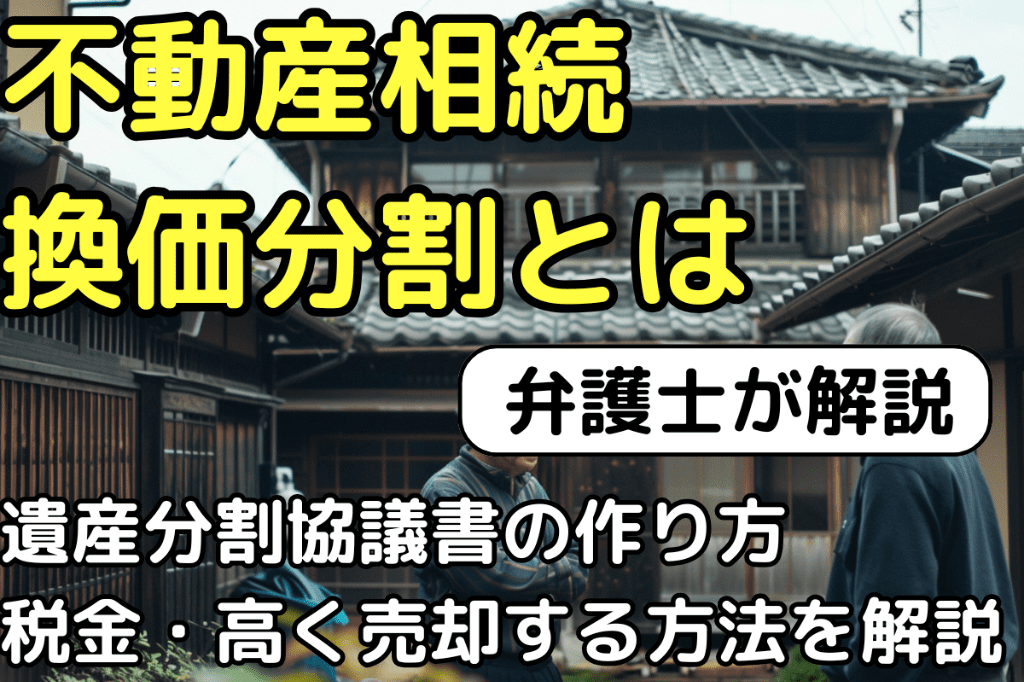
不動産を相続したとき、「どう分けるか」は相続人にとって大きな課題ですよね。
中でも「換価分割(不動産を売却して現金で分ける方法)」は、公平に分割できる反面、売却や税金、相続人間の調整など注意すべき点も多い方法です。
そこで、この記事では、相続で換価分割を検討している方が知っておくべき情報をわかりやすく整理しました。
この記事を読むことで、換価分割のメリットとリスクを正しく理解し、相続人全員が納得できる円満な遺産分割に進むための具体的なステップがわかります。
【この記事でわかること】
- 換価分割とは、不動産を売却して現金で分ける方法であること
- 他の遺産分割方法との違い
- 換価分割のメリット(公平性・紛争回避・柔軟な分割)とデメリット(売却価格・コスト・税金)
- 不動産を高く売却するためのポイントと不動産会社選びの注意点
- 換価分割の具体的な手順と遺産分割協議書の書き方
- 換価分割で発生する税金(相続税・譲渡所得税)と特例を活用した節税対策
- よくあるトラブル事例と未然に防ぐ方法
- 換価分割を成功させるために弁護士・税理士・司法書士など専門家に依頼すべき場面
なお、不動産を遺産分割する4つの方法(現物分割、代償分割、換価分割、共有分割)を詳しく知りたい方は、「不動産を遺産分割する4つの方法とは?円満な分割のコツと流れを解説」をご覧ください。
目次
1.不動産相続の「換価分割」とは何か?メリット・デメリット
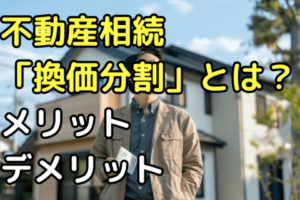
換価分割とは、不動産を第三者に売却して、その売却代金を相続人で分ける方法をいいます。
例えば、遺産の家と土地を3,000万円で売却して、3人の相続人が各1,000万円ずつ相続する方法です。
不動産をそのままの形で残すことはできませんが、公平で円滑な分割はしやすい方法と言えるでしょう。
なお、不動産の遺産分割は「換価分割」以外にも方法があります。
【遺産分割の4つの方法】
| 分割方法 | 説明 |
|---|---|
| 現物分割 | 不動産を相続人の1人が受け取る方法 |
| 代償分割 | 不動産を相続人の1人が相続し、他の相続人に代償金を支払う方法 |
| 換価分割 | 不動産を第三者に売却し、その売却代金を相続人で分ける方法 |
| 共有分割 | 不動産を相続人複数の共有にする方法 |
他の方法も含め、遺産分割の方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
関連:「不動産を遺産分割する4つの方法とは?円満な分割のコツと流れを解説」
1)換価分割のメリット
換価分割を選ぶメリットは3つあります。
➀公平な分割ができる
不動産はまったく同じ価値に分割することが出来ませんが、現金化することで1円単位まで同じ額に分割することが出来ます。
不動産を現金化する「換価分割」であれば、不動産の価値を明確にし、さらにそれを限りなく公平に分けられるのです。
これにより、他の分割方法よりも、相続人全員にとって公平性のある分け方ができるのです。
遺産分割で紛争となるのが公平性です。
したがって、相続人間で遺産を公平に分割できるのは大きなメリットです。
②紛争回避、トラブルが起きにくい
換価分割では、不動産を同額で公平に分割することができますから、相続人間での遺産分割がまとまりやすいです。
公平性というもっとも議論となるところが一つクリアになるために、相続人間での遺産分割紛争が生じにくいです。
遺産相続では、家族や親戚同士で揉めることを避けたい方が多いでしょうから、トラブルが起きにくい換価分割はおすすめです。
③柔軟な遺産分割ができる
遺産が現金化されることで、葬儀費用、納税費用、寄与分の調整、遺留分の調整など柔軟に使い分けることができます。
遺産に現金が少ない場合は、相続に伴う必要な支出を遺産から捻出することができません。
2)換価分割のデメリット
換価分割には3つのデメリット・注意点があります。
➀期待する金額で売れない可能性がある
不動産は水物といわれ、価格が変わりやすく結果予測が難しいです。
タイミングよくその不動産を喉から手が出るほど欲しい人が見つかるとものすごい高値で売れるかもしれません。
一方、タイミング悪くその不動産を欲しい人が見つからなかった場合は、価格を下げて買主を探さなければなりません。
場所によってはそもそも売れないということもあります。
ふたを開けてみないとわからないということです。
②売却にコストがかかる
不動産を売買するためには、買主を探してくる、買主と価格を含めた条件を交渉する、不動産登記をする、税金がかかると様々なコストがかかります。
買主を探し交渉するのに、不動産売買仲介料として、不動産売買価格の3%+6万円が必要です。
不動産登記をする費用として、司法書士への報酬と登録免許税がかかります。
不動産の売買価格が高くなればなるほどコストも比例して高くなります。
③譲渡所得税がかかる
相続によって取得することで相続税がかかるのはもちろんのこと、換価分割による不動産の売却によって、譲渡所得税がかかります。
相続税、譲渡所得税がかならずかかるということではなく、かからない場合もあります。
税金については、3章で詳しく解説します。
2.換価分割で遺産を高く売却(換価)する方法
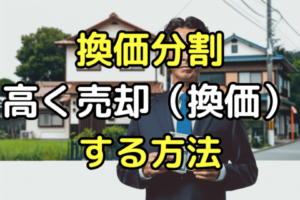
換価分割でもっとも重要なことは、不動産を高く速やかに売却することです。
相続人間で換価して遺産分割しようと決めたものの、なかなか売却できないとなると相続人間での紛争のタネになります。
また、高く売れれば売れるほど相続人の取り分が増えます。
1)重要なのは、不動産会社の選択
高く買ってくれる人を探してきてくれる不動産会社をどこにするかがもっとも重要なポイントです。
不動産会社の中には、自分のところで取扱いために、売れるかどうかを検討しないで高い査定価格を示したり、専属(専任)媒介にしてもらえれば高く売ってくるなどと適当なことをいってまで仲介契約しようとするところがあります。
一般的なポイントにはなりますが、以下を考慮して不動産会社を決めましょう。
- その地域での売買実績が多い
- 査定価格の根拠が明確かつ論理的
- 複数の業者が競争できる環境にする
- 仲介手数料をケチらない
たまたまその不動産が欲しくてたまらない人を知っていて交渉も出来そうだという場合を除いて、不動産会社がキモです。
慎重に良い不動産会社を選んでください。
3.換価分割の手順と遺産分割協議書の作成方法
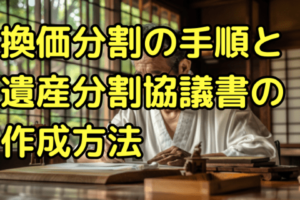
相続の発生から換価、分割終了までの手順を示します。
- 遺言書の確認と相続人の確定
- 遺産分割協議と換価分割の合意形成
- 遺産分割協議書の作成と換価分割の旨を記載する
- 不動産の相続登記(不動産名義変更)
- 不動産の売却
- 売却代金の分配と税金処理
相続税の申告は相続開始から10ケ月以内と期限があるため、上記順番に関わらず、期限までに申告と納税が必要です。
不動産の換価分割における遺産分割協議書と登記において注意点があります。
1)【ポイント①】不動産の登記名義人はどうする??
不動産を相続し換価分割するにおいて、その不動産の名義を相続人名義へ変更する登記をする必要があります。
被相続人は亡くなっており、不動産を売却することは不可能ですから、実際に不動産を売却する相続人名義への所有権移転登記が必要です。
では、どの相続人名義にするのかがですが、相続人全員の共有か代表となる相続人の単有かいずれかです。
2)【ポイント②】遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議で遺産の不動産を換価分割することになった場合、遺産分割協議書の書き方が2種類あります。
- 相続人全員の共有とする方法
- 代表となる相続人の単有とする方法
それぞれの違いや注意点などをみていきましょう。
①相続人全員の共有とする場合
相続人全員の共有名義として相続登記をする場合のメリットとデメリットをお伝えします。
メリットは、特定の相続人の売却代金の横領など不正を防ぐことが出来ることです。
1人の単独名義とすると、その人が手続きをして売却代金の受取りもすることになります。
納得いかない価格で売却された、売却代金の明細が不明瞭、売却代金を横領されたなどの問題が生じにくいです。
他方、デメリットとして、相続人全員が売却手続きの当事者となるため、交渉、売買契約、印鑑証明書などの書類の準備などあらゆる手続きを全員がすることになります。
また、誰か一人でも売却に異議を述べたら、その売却がとん挫してしまいます。
遺産分割協議書記載例
1 土地・建物については、Aが3分の1、Bが3分の1、Cが3分の1の割合で共有取得し、本遺産分割協議成立後5ケ月以内を目途に、換価分割する目的で売却する。
➀ 売却代金から売却にかかる費用(不動産仲介手数料、契約書作成費用、測量費用、登記手続費用、解体費用、残置物撤去・清掃費用、その他売却必要経費)を控除した残金を、A、B及びCが、各3分の1ずつの割合で受け取る。
② 売却までに要する修繕費、固定資産税等の維持管理費用、譲渡所得税等の売却にかかる租税は同割合での負担とする。
②代表となる相続人の単有とする場合
代表となる相続人の単有名義の相続登記をする場合のメリットとデメリットをお伝えします。
メリットは、売却当事者が一人となるため、その当事者が売却手続きを進められるため他の相続人の手間がなくなることです。
デメリットは、1人が売却手続きをすることができるため、不正される可能性があるということです。
遺産分割協議書記載例
1 土地建物については、換価分割を行うこととし、Aが単独で取得する。
➀ Aは、本遺産分割協議成立から5ケ月以内を目途に、同不動産を換価分割する目的で売却し、その売却代金から売却費用(不動産仲介手数料、契約書作成費用、登記手続費用、測量費用、解体費用、残置物撤去・清掃費用、その他売却必要経費)を控除した残金を、A、B及びCが各3分の1ずつの割合で配分する。
② 売却までに要する修繕費、固定資産税等の維持管理費用、譲渡所得税等の売却にかかる租税は同割合での負担とする。
いずれの選択をされた場合であっても、遺産分割協議書を作成し、換価分割であること、どのように分割するのかを記載してください。
4.換価分割で発生する税金と「賢い」節税対策
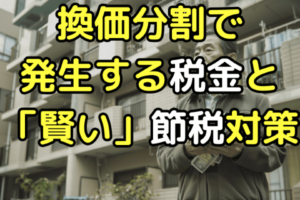
相続によって資産の移転が生じているため、相続税は当然かかる可能性があります。
そして、これに加えて、換価分割によって譲渡所得税が発生する可能性があります。
1)不動産売却で発生する譲渡所得税
譲渡所得税とは、資産の譲渡によって生ずる所得にかかる税金をいいます。
所得とは、売却額から取得費等の経費を差し引いたもので、ようはもうけをいいます。
相続によって不動産を取得し売却した場合に、被相続人がその不動産を取得した費用に売却諸経費を加えた額より高い額で売れるともうけが生じます。
譲渡所得の金額は、次のように計算します。
収入金額 – ( 取得費 + 譲渡費用) – 特別控除額 = 課税譲渡所得金額
この課税譲渡所得金額に、税率(保有期間によって異なる)をかけたものが税額となります。
ここでいう取得費は、被相続人が不動産を取得するにかかった費用です。
2)換価分割における譲渡所得税は誰が払うのか?
譲渡所得税は、売却した相続人が確定申告をして納付することになります。
したがって、相続人全員の共有名義にした場合は相続人全員、特定の相続人単独名義にした場合はその相続人となります。
ですが、換価分割の場合において、譲渡所得税を特定の人が負担するのは不公平ですから、相続人全員が公平に負担するように配分します。
3)換価分割で活用できる「特例」と節税対策
相続税に加えて、譲渡所得税がかかるのかと思ったかもしれませんが、特別控除を上手く用いることで税金が掛からない場合もあります。
譲渡所得税に使える特別控除の一例です。
- 空き家特例(租税特別措置法35条)
- 相続等によって空き家となった家屋を耐震リフォームまたは取り壊して売却した場合に3,000万円の特別控除がうけられます。
- 国土交通省のパンフレットにわかりやすく書かれています。
- 取得費加算の特例(租税特別措置法39条)
- この不動産を相続するために支払った相続税分を、売却時に取得費として控除できます。
- 国税庁が特例を受けられるかのチェックシートを出しています。
いずれの特例も大きなインパクトがありますが、いずれか一方しか使えないことに注意してください(租税特別措置法35条3項)。
また、譲渡所得税での特別控除ではありませんが、相続税の特別控除として、小規模宅地の特例があるので適用可能かを確認し、保有要件(相続税の申告期限まで保有)を満たすように換価分割を進めるかを検討してください。
特別控除等の措置を受けるためには要件があります。
換価分割の売却タイミング、価格などにおいて、これらの要件を満たすように検討が必要です。
売却後に気が付いても後戻りは出来ず、特例を受けられなくなります。
5.換価分割のトラブル事例と未然に防ぐ対処法
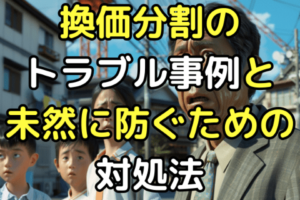
換価分割においてトラブルとなるのは実のようなことです。
- 売却価格の不一致
- 不動産会社選定への不満
- 税金負担の不公平
- 売却活動の遅延
- 相続人間の信頼関係の崩壊
- 適切な処理ができなくて贈与税の指摘を受ける
これらのトラブルを未然に防ぎ、「換価分割」を成功させるための方法をお伝えします。
- 徹底した情報共有
- あらゆることを透明化し、相続人全員が知れるようにする
- 売却状況、税金の見込みなど
- 意思決定の手順を確定させて、その手順とおりに行う
- 売却価格や業者選定の合意形成プロセス
- 遺産分割協議書など合意した内容の書面化
- 対立が起きた場合のルール設定
- 感情的な対立を避けるための話し合いの場
これらの対策をうつことで換価分割を成功させる可能性がぐんと高まります。
6.換価分割を成功させるための専門家利用
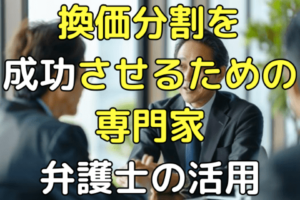
これまでの換価分割についての解説を読んでいただいて、ちょっと難しいかもと感じた方は、専門家を利用することをお勧めします。
不動産を売却する際は、不動産会社に相談、依頼してください。
また、特例の適用などを検討しながら売却額の配分と確定申告までを考えると、税理士へ相談です。
相続登記手続きについては、司法書士へ相談してください。
もっとも重要なことは、全体のプランを組むことです。
どこか一つの歯車が狂っても大きなトラブルになりかねません。
法律の専門家として全体のプランを考えたり、みなさんに代わって交渉できるのは弁護士です。
特に、
- 遺産分割協議がうまくいきそうもない
- 相続人が不仲である
- 相続前から財産の配分が不公平である
- 被相続人の財産を特定の相続人が管理していた
といった場合には、遺産分割に強い弁護士に相談することが有用です。
まとめ
不動産相続における換価分割は、不動産を売却して現金化し、その代金を相続人で分け合う方法です。現物分割や代償分割、共有分割と異なり、公平性を確保でき、紛争を回避しやすい点が大きなメリットです。相続人全員が同じ金額を受け取れるため、感情的な対立を抑えつつスムーズに遺産分割を進めやすい方法といえるでしょう。
一方で、換価分割には注意点もあります。希望通りの価格で不動産が売却できないリスク、仲介手数料や登記費用などの売却コスト、さらに譲渡所得税などの税金が発生する可能性があります。こうしたデメリットを理解し、適切に対応することが不可欠です。
換価分割を成功させるポイントは、不動産を少しでも高く売却できる不動産会社を選ぶこと、遺産分割協議書を正しく作成すること、そして節税につながる特例を逃さず活用することです。また、売却価格や税負担をめぐるトラブルを防ぐためには、相続人間での情報共有と合意形成が欠かせません。
しかし、相続手続きには不動産の売却、登記、税金の申告など多岐にわたる専門知識が必要です。途中で判断を誤れば、取り返しのつかない損失や深刻な相続トラブルに発展しかねません。
当事務所は、不動産相続や換価分割に豊富な実績を持ち、弁護士が全体のプランを監督しながら、税理士・司法書士など各専門家と連携して最適な解決をサポートします。「不動産相続を円満に解決したい」「換価分割で失敗したくない」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
早期に専門家へご相談いただくことで、安心して相続を進めることができます。


 お問い合わせ
お問い合わせ