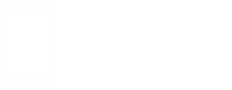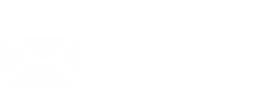- 最終更新:
代償分割とは?代償金の決め方と贈与税・相続税について弁護士が解説
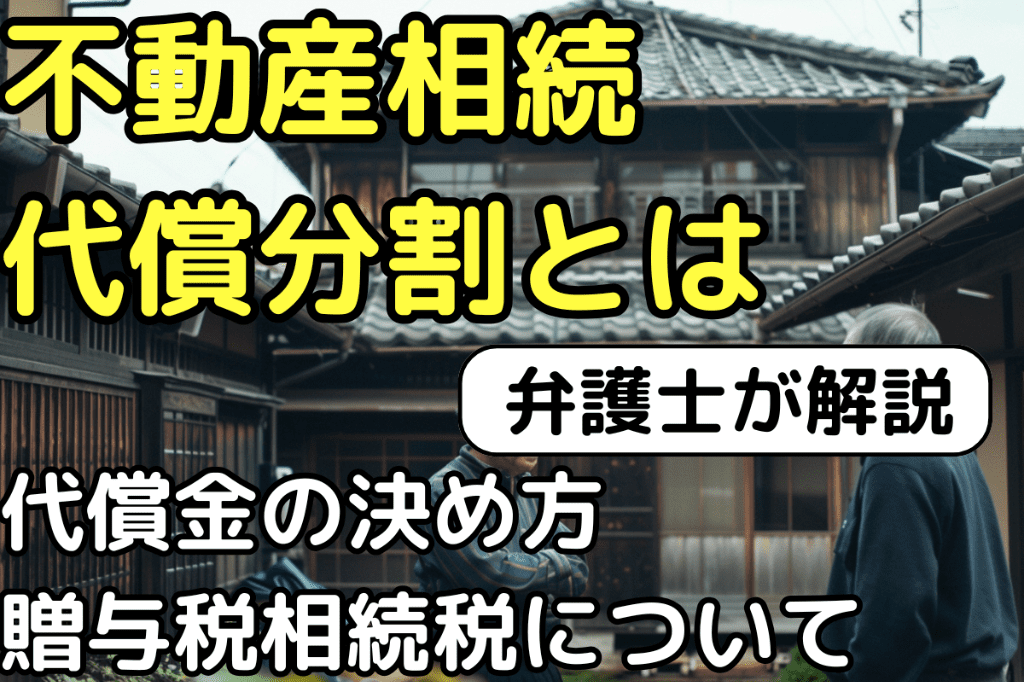
遺産に不動産が含まれていると遺産分割が難しくなります。
特定の相続人とってその不動産が必要であるが、その他の相続人にはその不動産が必要ではないという場合には、代償分割という方法をとることが有用です。
この記事では、代償分割をしようと考えている方に、代償分割とは何か、メリットデメリット、代償金の決め方、税金などを解説します。
【この記事でわかること】
- 不動産相続における「代償分割」とは、相続人が不動産を受け取る代わりに、他の相続人へ代償(現金など)を支払う分割方法をいうこと
- 代償分割のメリットは、不動産を手放さずに相続できる、共有名義による将来トラブルを避けられる、相続税の節税や納税資金の確保につながること
- 代償分割のデメリット・注意点は、不動産評価額を巡る揉めやすさ、代償金の支払い資金が必要になる、税務処理を誤ると贈与税等のリスクがあること
- 代償金の決め方、不動産の評価額の算定方法と、法定相続分に基づく金額の算出手順
- 代償分割と税金の関係(相続税・贈与税・所得税が問題となる場合や、小規模宅地の特例の活用可能性)
- 代償分割を円滑に進めるための具体的ステップ(不動産の評価方法の合意・第三者専門家の活用・遺産分割協議書の作成など)
弁護士や税理士に相談すべき場面(不動産評価額や税務リスクで揉めそうなとき、代償金の資金調達が難しいとき)
なお、不動産を遺産分割する4つの方法(現物分割、代償分割、換価分割、共有分割)を詳しく知りたい方は、「不動産を遺産分割する4つの方法とは?円満な分割のコツと流れを解説」をご覧ください。
目次
1.不動産相続の「代償分割」とは何か?メリット・デメリット
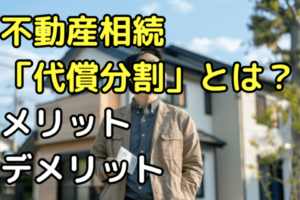
代償分割とは、相続人が不動産を受け取る代わりに、他の相続人へ代償(現金など)を支払う分割方法をいいます。
例えば、評価額3,000万円の不動産を、3人で分ける場合、長男が不動産を相続し、兄弟2人にそれぞれ1,000万円ずつ支払う方法です。
なお、不動産の遺産分割は「代償分割」以外にも方法があります。
【遺産分割の4つの方法】
| 分割方法 | 説明 |
|---|---|
| 現物分割 | 不動産を相続人の1人が受け取る方法 |
| 代償分割 | 不動産を相続人の1人が相続し、他の相続人に代償金を支払う方法 |
| 換価分割 | 不動産を第三者に売却し、その売却代金を相続人で分ける方法 |
| 共有分割 | 不動産を相続人複数の共有にする方法 |
他の方法も含め、遺産分割の方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
関連:「不動産を遺産分割する4つの方法とは?円満な分割のコツと流れを解説」
1)代償分割のメリット
代償分割を選ぶメリットは次の3つあります。
①大切な不動産を手放さずに済む
相続人が不動産を引き継ぐため、不動産を売却する必要がありません。
先祖代々の土地である、値上がりが期待できるなど処分したくない場合に有用です。
②不動産の共有名義による将来のトラブルを回避できる
1人の相続人が不動産を引き継ぐため、不動産を共有する必要がありません。
不動産を共有にすることは分割という意味では楽にできるのですが、今するべき分割協議の先送りになることが多く、将来的に紛争になる可能性が高まります。
このようにトラブルの元となる共有名義を使わなくて良いのが、大きなメリットです。
③相続税の節税など納税資金の確保にもつながる可能性がある
代償分割によって土地付き住宅を単独で相続する場合、要件を満たせば「小規模宅地の特例」の適用を受けられます。
この特例を受けることで土地の評価額を最大80%も減額できるため、相続税の大幅な節税が出来ます。
この特例の条件は、「実際にその家に住んでいる・住む予定がある相続人が単独で相続する」などです。
そのため、不動産を複数人で共有する方法よりも、1人が相続する代償分割の方が特例を使いやすい傾向があります。
また、代償分割では不動産を取得しない相続人に対して、代償金として現金を支払うことになります。
この仕組みによって、現金が含まれていない相続財産でも、他の相続人に現金が渡る形になります。
その結果、代償金を受け取った側は、相続税の納税資金を確保しやすくなるというメリットがあります。
2)代償分割のデメリット・注意点
代償分割には3つのデメリット・注意点があります。
①不動産の評価額を巡る合意形成の難しさ
代償分割は、不動産を相続する相続人が、その不動産相当額を現金等(代償金)で他の相続人に支払うことになります。
この「代償金をいくらにするか」という点で、揉めやすいのが大きな注意点になります。
不動産を相続する相続人は、支払う金額を少なくしたいと考えますから、不動産を出来る限り安く評価します。
他方、他の相続人は、もらう金額を多くしたいと考えますから、不動産を出来る限り高く評価します。
ここに相続人間の対立が生まれてしまいます。
この不動産の評価額(代償金に直結する)については、代償分割する上で1番大きな問題ですので、次の項目で改めて詳しく解説します。
②代償金を支払う資金が必要になる
不動産を相続する相続人は、他の相続人に対して代償金を現金で支払うことが多いです。
この代償金は、不動産の評価額や相続人の人数によっては、数百万円〜数千万円規模になることもあります。
また、不動産をそのまま相続するということは、当然ながらその不動産を売却して資金にすることもできません。
従って、十分な現金等をもっていないと、代償金を支払うことが難しいということになります。
③手続きの適正処理が必要(贈与税・相続税)
不本意な税金がかからないように、遺産分割における代償分割であることが明確にわかるようにしましょう。
代償分割では、不動産を相続する相続人の財産、遺産ではない財産が移転します。
ですから、相続人間の財産の移転について、贈与税、所得税などの問題が出てきます。
詳しくは、3章で解説します。
2.代償分割における「代償金」の決め方
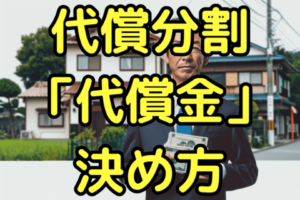
不動産を代償分割する上で、もっとも大きなポイントになるのが、「代償金の決め方」です。
代償金の金額は、①まず遺された不動産の評価額を算出し、②その評価額を法定相続分に従って各相続人に分けることで決められます。
以下では、この手順を2つのポイントに分けて説明します。
1)【ポイント①】不動産の評価額を出す
代償金の金額を決めるにはまず、そもそも分ける不動産の評価額を知るところから始めます。
不動産の評価方法にはさまざまな種類があり、どの評価方法を採用するかによって評価額が大きく異なります。
【不動産の評価方法】
- 固定資産税評価額
- 相続税評価額(路線価)
- 不動産鑑定評価額
これらの評価方法のいずれを用いるかによって不動産の評価額が変わるため、相続人全員で評価方法を合意しておくことが重要です。
特に代償分割の場合、その評価額で相続人で利益が相反するので、揉めないように注意しましょう。
自分が得をするかどうかだけでなく、全員が納得できる評価方法をとりましょう。
不動産の評価方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
関連:「遺産分割での不動産の3つの評価額・評価方法!基準時についても解説」
2)【ポイント②】法定相続分に沿って分ける
法定相続分とは、民法で定められた遺産分割の目安となる割合のことです。
法定相続分は相続人の組み合わせによって異なり、相続人のパターンごとの法定相続分は、下表のとおりです
| 相続人の組み合わせ | 法定相続分の割合 (相続人ごとの取り分) |
|---|---|
| 子どものみ | 子ども: 1/1(※相続財産の全部を子どもたちで均等に分ける。例: 子ども2人なら各1/2ずつ) |
| 配偶者+子ども | 配偶者: 1/2、子ども: 1/2(※子どもが複数いる場合はこの1/2を均等に分け合う) |
| 配偶者+被相続人の親(直系尊属) | 配偶者: 2/3、親: 1/3(※親が複数いる場合はこの1/3を均等に分け合う) |
不動産の評価額と各人の法定相続分が分かれば、代償金の支払いを計算できます。
不動産を現物で取得する人は、他の相続人それぞれに対し、その人の法定相続分に相当する金額を代償金として支払います。
例えば、価値が2,000万円の不動産を子ども2人が相続する場合、一方の子が不動産を取得したときは、もう一方の子に対して1,000万円の代償金を支払うことになります。
3.代償分割と税金
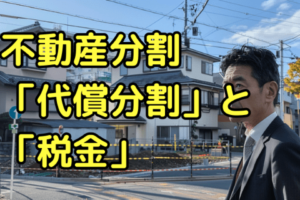
相続なんだから相続税だけの問題ではないのと思われるかもしれませんが、他の税金がかかる可能性があることに注意が必要です。
例えば、代償分割によって、金銭を支払ったのであれば、原則として贈与税などはかかりません。
ですが、代償分割によって、金銭以外のものを渡した場合は、それを売却したのと同様ですから、所得税がかかる可能性があります。
つまり、そのものを取得時よりも高い評価として渡した場合に値上がり益があるということです。
また、渡す金銭が不動産に比して高すぎる場合には、代償分割に隠れた贈与ではないのかとツッコミが入り、贈与税がかかる可能性があります。
4.代償分割を円滑に進めるための具体的なステップ
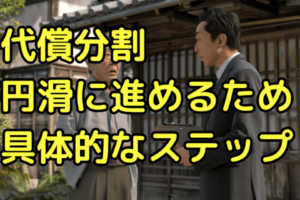
では代償分割を円滑に進める遺産分割協議の具体的なステップを解説します。
- Step 1:遺産内容と相続人の確定
- Step 2:相続人間で遺産、不動産に関わる情報を共有する
- Step 3:代償分割による方法を検討し、相続人間で合意する
- Step 4:不動産を評価する方法を相続人間で合意する
- Step 5:評価額が出た後でその額に異論を述べないと合意する
- Step 6:誰の知り合いでもない第三者の専門家に対して、全相続人で依頼をする。
- Step 7:不動産の評価額の決定
- Step 8:遺産分割協議書の作成、代償金の金額と支払い方法の決定
- Step 9:後手続(不動産の名義変更、相続税申告、代償金の支払い)
ポイントは、後出しじゃんけんをしないことです。
つまり、相続人間でどう評価するか合意がないまま、地元の不動産屋に評価を出してもらうと、評価が出た後にその金額が妥当ではないと議論することになります。
また、最後の詰めが甘かったとならないようにお願いします。
不動産鑑定士に依頼するときも、1人の相続人から依頼でなくて全員で依頼します。
なぜなら、依頼する相続人が、こういう方向で評価をして欲しいというと一定の操作ができてしまいますし、そのような懸念を他の相続人が持たないようにするためです。
5.こんな時は迷わず弁護士・税理士へ
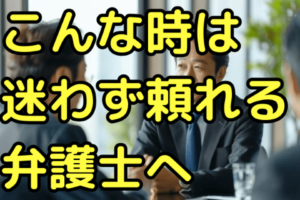
遺産の内容や相続人の状況から代償分割しか選べないということもあるでしょう。
代償分割をするという場合は、そのタイミングで弁護士へご相談されることをお勧めします。
不動産は価格が大きくなりますし、代償分割による相続人間の利益相反がありますから、トラブルになることが予想されます。
また、揉め初めた時点は、弁護士への相談をぜひしてください。
早く対応することが問題を円滑に早く終わらせることになります。
また、相続税申告に関する不動産の評価額は、代償分割の際に用いる評価とは別になります。
相続税は、所得税、贈与税と同様に最高税率が55%です。
税理士に相談するなど慎重に対応してください。
まとめ
不動産相続において、遺産分割は相続人間の合意形成を要する極めて重要な手続きです。その中で「代償分割」は、相続人の一人が不動産を取得し、他の相続人へ代償金を支払うことで公平性を確保する分割方法です。先祖代々の土地や自宅を守りつつ、共有名義による将来的な紛争を回避できるという大きな利点があります。また、要件を満たせば小規模宅地の特例を活用でき、相続税の節税や納税資金の確保にもつながる点は見逃せません。
もっとも、代償分割は一見シンプルに見えて、実務上は難しい判断を伴います。不動産の評価額は固定資産税評価額・路線価・不動産鑑定評価額など複数の基準があり、その選択によって金額が大きく変動します。評価額は代償金に直結するため、相続人間の利害が対立しやすい最大のポイントです。さらに、代償金の資金調達や支払い方法も大きな課題であり、場合によっては金融機関からの借入を検討せざるを得ないケースもあります。
税務面でも慎重な対応が求められます。代償分割で金銭以外の財産を移転すれば所得税課税の可能性があり、また評価額が不自然に高額であれば贈与とみなされるリスクもあります。相続税申告との整合性を欠けば、後に税務調査の対象となることも考えられます。このように、代償分割は法的・税務的観点の両面から高度な判断を必要とするのです。
結論として、代償分割は不動産相続における有効な手段である一方、評価・資金・税務の三点で専門的な調整が不可欠な方法です。適切な手続きを進めるためには、弁護士や税理士といった専門家の関与が実務上ほぼ必須といえるでしょう。不動産相続の公平かつ円滑な実現には、専門的知見に基づいたサポートを得ながら進めることが最も確実な方法です。


 お問い合わせ
お問い合わせ